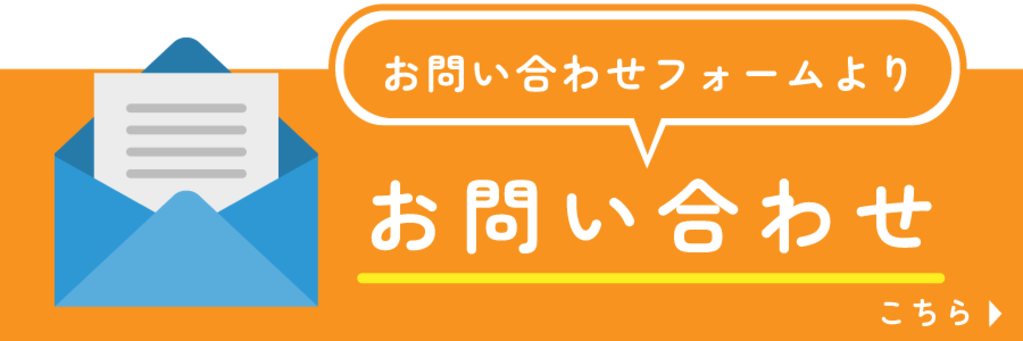eギフトとは?働き方・顧客体験を変える"デジタルインセンティブ"の新潮流

目次[非表示]
\ デジタルインセンティブのご相談はこちらから /
いま、ビジネスの"贈り方"が変わっている
近年、企業活動における「贈り物」のあり方が大きく変化しています。
コロナ禍による非対面でのコミュニケーション や、働き方の多様化により、従来の手渡しの贈答文化は見直しを迫られました。
オンラインによる会議やリモートワークなどが一般化する中、企業は顧客や取引先、従業員とのつながり方を再設計する必要に迫られています。
そんな中で注目を集め、一般化してきているものが 「eギフト」という新しい選択肢です。
■ 「贈る」行為がオンラインに移行している
これまでのギフトは、「包装されたモノ」を「対面で手渡す」ことが前提でした。
一方で、現代のビジネスシーンでは「非対面」「即時性」「管理のしやすさ」が求められています。
こうした背景から、ギフトの“体験”自体をオンライン化する流れが加速しており、企業も続々とデジタルギフト(eギフト)を取り入れ始めています。
■ 「会わなくても、気持ちは伝えられる」時代へ
eギフトは単に「モノを贈る手段」ではありません。
それは、企業の姿勢や感謝の気持ちを伝えるコミュニケーションツールでもあります。
- お客様への「ちょっとしたお礼」
- 社員の頑張りへの「報奨や労い 」
- 見込み顧客との「ファーストタッチ」
- 直接会えなくても、心のこもった一言と共に、スマートに気持ちを届ける。
その"新しい贈り方"こそが、eギフトの価値なのです。
次章では、そもそも「eギフトとは何か?」について、ビジネスにおける活用を前提とした解説をしていきます。
本質を理解することで、活用のアイデアもより広がっていくはずです。
eギフトとは?ビジネス活用における基本と仕組み
eギフトとは、「贈り物(ギフト)」をデジタル環境で送ることができるサービスです。
従来のように実物を手渡しする必要がなく、オンライン上で贈ることができるため、現代の多様化した働き方や非対面コミュニケーションの増加に対応した新しい形のギフトです。
以下では、eギフトの基本的な仕組みや特徴、法人利用における利点について詳しく解説します。
eギフトの基本的な仕組み
eギフトの利用手順は非常にシンプルで、贈り手と受け取り手の双方にとって負担が少ないのが特徴です。
贈り手
- ギフト選択:専用プラットフォームやオンラインショップ から贈りたいギフトを選びます。選択肢には、コンビニドリンクや百貨店の商品券、ECサイトポイント、体験型ギフトなどがあります。
- メッセージ添付:感謝や祝福の気持ちを伝えるメッセージを添えることができます。
- 送信:メールやSNSを通じてURL形式でギフトを送信します。
受け取り手
- URL受信:メールやSNSで送られてきたURLを開きます。
- 引き換え:店舗で提示するか、オンラインで利用して商品やサービスと交換します。
このプロセスでは住所や電話番号などの個人情報を取得する必要がないため、プライバシー保護の観点でも安心して利用できます。また、リアルタイムで贈り物が届くため、即時性にも優れています。
eギフトの種類
eギフトは幅広い商品やサービスに対応しており、多様なニーズに応えることが可能です。
以下は主なカテゴリです。
- 商品交換型 型ギフト:コンビニエンスストアの商品券や特定の商品引換券(例:ドリンクチケット)。
- 体験型ギフト:レストラン予約券やアクティビティ体験券。
- ポイント型ギフト:ECサイトで利用可能なポイント。
- エンターテインメント型ギフト:映画や本などのエンターテインメントに使える電子ギフトです。(例:映画の割引チケットや図書カードなど)
これらは個人間だけでなく法人利用にも適しており、さまざまな場面で活用されています。
法人利用における利便性
法人がeギフトを活用することで得られるメリットは多岐にわたります。
特に、「誰に」「何を」「いつ」「どのように」贈るかを柔軟に設計できる点が、大きな強みです。
業務効率化
ギフト管理がオンライン上で完結するため、従来必要だった在庫管理や配送手続きが不要になります。
一括購入機能や利用履歴の可視化機能を備えた法人向けサービスもあり、大量配布にも対応可能です。
コスト削減
実物の商品を発送する際に発生する梱包・配送費用が不要となります。
必要な分だけ購入し、未使用分は再利用できる仕組みも多くのサービスで提供されています。
安全性
住所や電話番号など個人情報を取得せずに送れるため、セキュリティリスクが軽減されます。
コンプライアンス面でも安心して運用可能です。
eギフトがもたらす新しい価値
Eギフトは単なる「モノ」を贈る行為から、「体験」や「気持ち」を届ける行為へと進化しています。
以下のような新しい価値観を企業活動にもたらします。
即時性と柔軟性
リアルタイムで相手に気持ちを伝えられるため、迅速な対応が求められるビジネスシーンでも活躍します。贈り先の好みに応じてカスタマイズ可能な点も魅力です。
パーソナライズされたコミュニケーション
メッセージカード機能やブランドロゴ入り配信画面などによって、受け取る側に特別感を与えることができます。これにより企業イメージ向上にもつながります。
環境への配慮
紙資源や梱包材を使用しないため、環境負荷が軽減されます。
サステナビリティへの取り組みとしても評価されます。
マーケティングツールとしての活用
eギフトは顧客満足度を高めるマーケティングツールとしても利用できます。
特にデジタルギフトサービス「mafin」はマーケティング支援に役立つデジタルギフトサービスです。
eギフト活用事例
個人向け
誕生日プレゼントとしてスターバックスのドリンクチケットを贈る。
出産祝いとしてカタログ型eギフトを送付。
法人向け
・顧客向けキャンペーン
購買促進キャンペーンの景品としてeギフトコードを配布し、新規顧客獲得につなげる。
・従業員インセンティブ
成績優秀者への報酬としてeギフトを配布し、モチベーション向上を図る。
・取引先への感謝状代わり
年末年始の挨拶として取引先へeギフト付きメッセージカードを送付し関係性強化。
eギフトはデジタル時代ならではの利便性と柔軟性を兼ね備えた新しい贈り物の形です。
特に法人利用では、効率的かつ効果的なコミュニケーションツールとして多くの企業から注目されています。その簡便さ、安全性、多様性から今後さらに普及していくことが予想されます。
法人利用が広がる理由(ビジネス的メリット)
Eギフトの法人導入が進んでいる背景には、いくつかの明確なメリットがあります。
従来のギフト提供方法では、配送や在庫管理、コスト面で課題がありましたが、デジタル化されたeギフトはこれらの問題を解決し、企業活動を効率化する新たな選択肢として注目されています。
以下では、社内向けと社外向けに分けて、その具体的な活用例とビジネス的メリットを詳しく解説します。
社内向け:従業員エンゲージメントの向上
従業員へのモチベーション向上や感謝の気持ちを伝えること を目的として、eギフトは多くの企業で活用されています。
特にテレワークやリモートワークが一般化した現在では、従業員とのコミュニケーションを円滑にし、エンゲージメントを高める手段として効果的です。
1. 業績や行動に対するインセンティブ
eギフトは、従業員の成果や行動に対するインセンティブとして即時配布可能です。
例えば、目標達成時や特定のプロジェクト完了時に贈ることで、努力をリアルタイムで評価しモチベーションを維持できます。
従来の現物報酬と異なり、受け取る側が自由に選べる形式のため満足度が高くなります。
2. 誕生日や記念日のお祝い
福利厚生の一環として従業員の誕生日や記念日にeギフトを贈ることで、個人への配慮を示すことができます。カフェチケットやスイーツなどの気軽なアイテムが人気であり、特別感を演出しつつ気軽に利用できる点が魅力です。
3. テレワーク下でのモチベーション維持
リモート環境では直接的なコミュニケーションが減少するため、eギフトによる感謝の可視化は重要です。例えば、「ありがとう」や「お疲れ様」といったメッセージ付きで贈ることで、心理的な距離感を縮める効果があります。
配布作業がオンラインで完結するため、人事部門や管理者にとっても負担が少ない点が利点です。
社外向け:営業・マーケティング施策の効率化
顧客や取引先との関係性強化やマーケティング施策にもeギフトは大きな効果を発揮します。
特に営業活動やキャンペーン設計において、その効率性と柔軟性が評価されています。
1. 商談成立時のフォローギフト
新規商談成立後のお礼としてeギフトを贈ることで、取引先との関係性を強化できます。例えば、「本日はお時間いただきありがとうございました」といったメッセージと共に贈ることで好印象を与えます。
ギフト内容は相手企業の規模や担当者の好みに合わせてカスタマイズ可能です。
2. セミナー参加やアンケート協力への謝礼
セミナー参加者への謝礼としてeギフトを配布することで参加意欲を高められます。
また、アンケート回答者にも同様にインセンティブとして提供することで回答率向上につながります。
配布がURL形式で完結するため、大規模イベントでも手間なく対応可能です。
3. 購買促進キャンペーンへの組み込み
eギフトは購買促進キャンペーンにおいても効果的です。例えば、新規購入者に対してポイント型ギフトを贈ることでリピート購入を促進します。
また、SNSキャンペーンでフォロワー限定ギフトを提供することでブランド認知度向上にも寄与します。
eギフト導入による総合的メリット
Eギフトは「低コスト・高効果」のコミュニケーション手段として、多くの企業から注目されています。
その総合的なメリットについてさらに詳しく見ていきます。
1. 業務効率化
ギフト管理がオンライン上で完結するため、従来必要だった在庫管理や配送手続きが不要になります。
一括購入機能や利用履歴の可視化機能を備えた法人向けサービスもあり、大量配布にも対応可能です。
2. コスト削減
配送費用や梱包費用など現物ギフト特有のコストが発生しないため、大幅な経費削減につながります。
少額から利用可能なサービスも多く、予算に応じた柔軟な運用が可能です。
3. 安全性
住所や電話番号など個人情報を取得せずに送れるため、セキュリティリスクが軽減されます。
コンプライアンス面でも安心して運用可能です。
法人利用事例:成功した活用例
以下は実際にeギフト導入によって成功した法人利用事例です。
従業員表彰制度
成績優秀者へのインセンティブとしてリアルタイム配布。
これにより従業員満足度(ES)が大幅に向上した企業があります。
取引先との関係性強化
年末年始の挨拶として取引先へeギフト付きメッセージカードを送付し継続契約率アップにつながった事例があります。
顧客ロイヤルティプログラム
CRMデータと連携して誕生日・記念日に自動送信し顧客満足度向上。
これによりリピート率増加した企業もあります。
法人利用におけるeギフトはその柔軟性と利便性から、多様な場面で活躍しています。
従業員エンゲージメント向上から営業・マーケティング施策まで幅広く対応できるこのツールは、「効率化」「コスト削減」「安全性」の観点からも優れた選択肢と言えます。
今後さらに普及し、多くの企業活動で欠かせない存在になるでしょう。
eギフト活用シーン9選(法人編)
eギフトは、法人活動において幅広いシーンで活用されており、その利便性と効果の高さから注目を集めています。
以下では、具体的な活用例を9項目に分けて詳しく解説します。
それぞれの事例がどのように企業活動を支援し、効率化や関係性強化に寄与しているかを掘り下げます。
1. イベント参加者への謝礼
セミナーや展示会などのイベントに参加した顧客や取引先への謝礼として、eギフトを即時配布する方法が広く採用されています。例えば、セミナー終了後に参加者へドリンクチケットをメールで送ることで、手間をかけずに感謝の気持ちを伝えることができます。この方法は、参加者の満足度向上だけでなく、次回イベントへの参加意欲を高める効果も期待できます。
具体例:
- 展示会来場者にカフェチケットを配布し、ブランドイメージ向上。
- セミナー終了後のアンケート回答者へのインセンティブとして商品券を提供。
2. 新規商談後のフォローアップ
新規商談後にeギフトを贈ることで、第一印象をさらに強化し、取引先との関係性構築を支援します。例えば、「本日は貴重なお時間をいただきありがとうございました」というメッセージと共に贈ることで、相手に好印象を与えます。このようなフォローアップは、商談成立率や継続契約率の向上につながります。
具体例:
- 商談後にコンビニ商品券を贈り、相手企業との関係性強化。
- 初回訪問時に体験型ギフトを贈り、ブランドの特別感を演出。
3. 定期契約の継続促進
定期契約更新月に合わせてeギフトを贈ることで、契約継続率を向上させる施策として活用されています。例えば、「いつもご利用ありがとうございます」というメッセージと共に贈ることで、顧客ロイヤルティを高めることが可能です。CRMデータと連携すれば、自動送信による効率的な運用も実現できます。
具体例:
- サービス更新月にAmazonギフトカードを贈り、顧客満足度向上。
- 長期契約顧客への特別ギフト提供でロイヤルティ強化。
4. 顧客の誕生日・記念日対応
顧客の誕生日や記念日にeギフトを贈ることで、特別感と親密さを演出します。CRMシステムと連携することで、自動送信が可能となり、一人ひとりの顧客にパーソナライズされた体験を提供できます。この施策はリピート率やブランドロイヤルティ向上にも寄与します。
具体例:
- 誕生日にカフェチケットやスイーツギフトを自動送信。
- 記念日に体験型ギフト(例:レストラン予約券)を提供。
5. 社内の表彰制度に組み込む
従業員表彰制度にeギフトを組み込むことで、成績優秀者や貢献度の高い従業員へのインセンティブをリアルタイムで提供でき、従業員満足度(ES)の向上や職場環境の改善が期待できます。
eギフトは、その場で努力や成果が評価される特別感を演出し、モチベーションの可視化や維持に効果的です。また、個別対応が可能なため、一人ひとりの貢献や日々の努力にも柔軟に報いることができ、従業員のエンゲージメント向上にも寄与します。
成績や貢献だけでなく、日常の努力やチームワークも評価対象とすることで、全従業員のモチベーションアップや理想の社員像の浸透、愛社精神の向上につながります。
選考基準を明確にし、個人・チーム両方の成果を公平に評価することで、納得感の高い制度設計が実現できます。
具体例:
- 年間MVP受賞者へ高額eギフト券を提供。
- 月間優秀者へカジュアルなドリンクチケットを配布。
- 営業目標達成時にAmazonポイントコードを配布。
- チーム単位でプロジェクト成功時に体験型ギフトを提供。
6. 福利厚生制度の充実
福利厚生制度としてeギフトを導入することで、従業員が手軽にリフレッシュできる環境づくりが可能です。例えば、「いつもお疲れ様です」というメッセージ付きでカフェチケットやスイーツ引換券を贈ることで、従業員満足度向上につながります。
具体例:
- カフェチケット配布による休憩時間の質向上。
- スイーツ引換券提供によるリフレッシュ促進。
福利厚生の以下の関連記事もぜひごらんください。
7. 採用活動時のリファラル報酬
採用活動で紹介者へeギフトを迅速に提供することで感謝の気持ちを伝えつつ、その場で報酬として機能させることが可能です。この施策は紹介活動促進だけでなく採用プロセス全体の効率化にも寄与します。
具体例:
- 紹介成功時に即座にAmazonギフトコード送付。
- 採用イベント参加者への謝礼としてカジュアルな商品券提供。
8. 退職者への贈り物
退職者へ感謝と敬意を示す文化づくりとしてeギフトは効果的です。
例えば、「これまでありがとうございました」というメッセージと共に贈ることで円満退職につながります。また、この文化は企業イメージ向上にも寄与します。
具体例:
- 退職記念品として高額商品券提供。
- 長年勤務した従業員へ特別な体験型ギフト提供。
9. 販促キャンペーンの景品提供
販促キャンペーンで景品としてeギフトコードを即時配布することで、新規顧客獲得や購買促進につなげられます。この方法は手間なく大量配布可能なため、大規模キャンペーンでも効果的です。
具体例:
- SNSフォロワー限定キャンペーンでドリンク引換コード配布。
- 購買金額条件付きキャンペーンで商品券提供。
eギフト活用による総合的な価値
これら10項目は一部ではありますが、それぞれ異なる目的や対象層へのアプローチ方法として機能しています。eギフトは「贈る手間」を省きつつ、「印象」を強く残すツールとして幅広い場面で活躍しており、その柔軟性と利便性から今後さらに普及していくことが期待されます。
よくある懸念とその解決策(ビジネスの不安を払拭)
【セキュリティは大丈夫か?】
住所や電話番号などの個人情報を取得せずに贈れる仕組みのため、 個人情報保護の観点でも安心して導入が可能です。
【ギフトなのに味気なくならないか?】
メッセージカードの添付やブランディングされた配信画面の活用により、 パーソナライズされた温かみあるコミュニケーションが可能です。
【経費処理や業務フローに支障が出ないか?】
法人専用サービスであれば請求書払い、一括管理、利用履歴の可視化が標準対応されている事業者も。
サービス各社への問い合わせ時に確認しましょう。
eギフト×マーケティング戦略の可能性
eギフトは単なる「贈り物」にとどまらず、マーケティング施策との親和性が非常に高いツールです。
企業が顧客との接点を強化し、ブランド価値を高めるための戦略として、多岐にわたる活用方法を提供します。本章では、具体的な活用例やその効果について詳しく解説します。
eギフトのマーケティング活用の強み
1. 顧客体験の向上
eギフトは、デジタル環境で完結するため、迅速かつ手軽に顧客へ贈り物を届けることができます。顧客はストレスなく商品やサービスを受け取り、ポジティブなブランド体験を得られます。特に、住所不要で贈れる仕組みは、SNSやメールを介したキャンペーンで大きな効果を発揮します。
2. ブランド認知度の拡大
SNSキャンペーンやインフルエンサー施策と組み合わせることで、ブランド認知度を効率的に拡大できます。「フォロー&リポスト」や「友達にギフトを贈るとクーポンがもらえる」といったプロモーション形式は、自然な形で商品の拡散と新規顧客獲得につながります。
3. LTV(顧客生涯価値)の向上
一度きりの購入促進だけでなく、リピート購入やロイヤルティ向上にも寄与します。例えば、初回購入者への限定ギフトや会員ランクアップ施策として活用することで、顧客との長期的な関係構築が可能です。
eギフト活用の具体例
1. 初回購入者への限定ギフト
新規顧客へのアプローチとして、初回購入時にeギフトを提供する方法があります。
例えば、「初めてのご利用ありがとうございます」というメッセージと共にドリンクチケットやポイントを贈ることで、新規顧客の満足度を高めます。
2. SNSキャンペーンの参加特典
SNSキャンペーンでは、参加条件として「フォロー&リポスト」や「いいね」を設定し、その特典としてeギフトを提供する方法が人気です。この形式は拡散力が高く、多くのユーザーにリーチできるため、新規フォロワー獲得やエンゲージメント向上に効果的です。また、インスタントウィン型キャンペーンでは、その場で当選通知と共にeギフトが配布されるため、参加者満足度がさらに高まります。
3. レビュー投稿インセンティブ
商品やサービス利用後のレビュー投稿促進にもeギフトは有効です。
例えば、「レビュー投稿で500円分のeギフトプレゼント」といった施策を行うことで、多くのユーザーからフィードバックを集められます。この方法はECサイト運営者にとっても重要なデータ収集となります。
4. 会員ランクアップ施策
会員プログラム内でランクアップ時の特典としてeギフトを提供することで、顧客満足度とロイヤルティを向上させます。例えば、「ゴールド会員になると1,000円分のeギフトプレゼント」という形で動機付けを行うことが可能です。このような施策は継続利用率向上にも寄与します。
eギフト活用によるマーケティング効果
1. データドリブンなアプローチ
eギフト活用では、顧客データ(購買履歴や行動データ)との連携が容易であり、それに基づいたパーソナライズされた提案が可能です。例えば、「過去6ヶ月間購入履歴がない顧客」に対して限定キャンペーンとしてeギフトを送付し再訪問を促す、といった施策も実現できます。
2. ブランドイメージ向上
広告ではなく友人から贈られたギフトという形でブランド商品に触れることで、受け取った側にはポジティブな印象が残ります。このような体験型マーケティングは従来型広告よりも効果的であることがデータでも示されています。
3. コスト削減と柔軟性
従来の物理的な販促品や景品とは異なり、eギフトは発注から配送まで全てオンラインで完結するため、大幅なコスト削減が可能です。また、小額から大量発注まで柔軟に対応できるため、小規模イベントから大規模キャンペーンまで幅広く活用できます。
eギフト×マーケティング戦略の未来
Eギフトは単なる「贈り物」ではなく、「体験」を通じてブランド価値を高めるマーケティングツールです。SNSやECサイトとの連携によって新規顧客獲得からロイヤルティ向上まで幅広い用途で活用されており、その効果は多くの成功事例からも明らかです。
今後もデジタル技術との融合が進む中で、さらに多様な形態で企業活動に貢献していくでしょう。
\ デジタルインセンティブのご相談はこちらから /
これからのギフトは「企業ブランディング」の一部になる
今後、eギフトは単なるツールではなく、企業の価値観や文化を伝える手段としての役割を担っていくでしょう。
「ありがとう」「よくがんばったね」「また会いたい」
こうした短い言葉と共に、ギフトを添える文化は、企業のホスピタリティやカルチャーを象徴する重要なタッチポイントです。
企業ブランドは、社外だけでなく社内にも"語りかけるもの"。
eギフトを活用することは、あらゆる関係者との関係性を育み、 組織としての信頼感・愛着・一体感を高めることに繋がっていくのです。