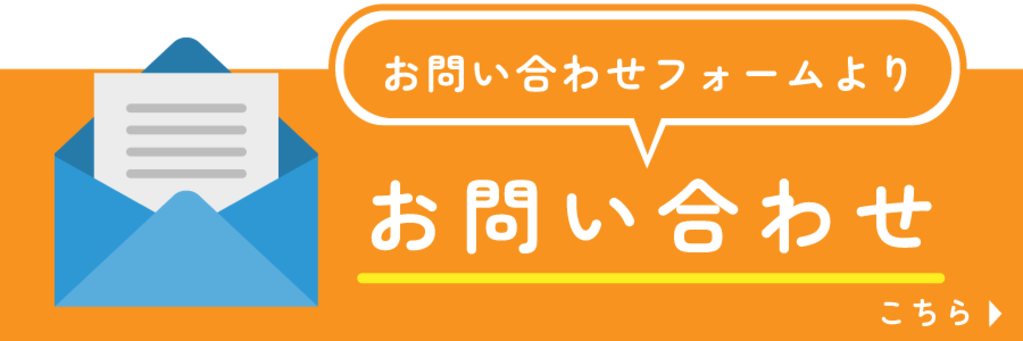キャンペーン担当者必見! 「景品表示法」とは? 基礎から最新法改正への対応策まで

目次[非表示]
景品表示法の基本概要と目的をわかりやすく解説
景品表示法とは
景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)は、広告や販促活動において 消費者に誤解を与える表現や過大な景品提供を防ぐための法律です。
簡単にいえば、「宣伝は正しく、景品は適正に」というルールで、市場の公平性と消費者の信頼を守ることが目的です。
例えば、実際より効果があるように見せる広告や、購入意欲を不当にあおる高額景品(取引の価値に対して過大な景品など)は、この法律で規制されます。
景品表示法を構成する2つの規制
景品表示法は、次の2つの規制(仕組み)で消費者と市場の健全性を守ります。
1 . 不当な表示の防止(表示規制)
商品・サービスの品質、価格、条件などを実際以上に良く見せたり、事実と異なる情報を表示したりすることを禁止します。
例:「通常価格10,000円」→ 実際はその値段で販売した実績がない
例:「飲むだけで必ず痩せる」→ 科学的根拠がない
2 . 過大な景品提供の制限(景品規制)
買うかどうかの判断に不当に影響を与えるような高額・過剰な景品を規制します。
景品には上限額があり、条件によっては提供できる金額や内容が決まっています。
適用範囲と対象
業種や規模を問わず、一般消費者向けに商品やサービスを提供する事業者に適用されます。
テレビCM、大手ECサイトのセール告知、SNSキャンペーン、店舗の価格POPなど、日常的に行っている宣伝活動も対象です。
管轄と違反した場合のペナルティ
この法律の運用は「消費者庁」が行い、違反が発覚すると以下のような措置が取られることがあります。
- 措置命令:不当表示などがあった場合、消費者庁は表示内容の是正(訂正・削除など)を命じ、その違反事実を公表します。
- 課徴金納付命令:優良誤認表示や有利誤認表示に対しては、違反行為により得た売上額の最大3%を課徴金として納付する命令が出されることもあります。
- 再発防止命令・調査命令:今後同様の違反を繰り返させないための措置命令や、事実関係を明らかにするための調査命令も行われます。
金銭的負担だけでなく、企業名の公表によるブランド毀損や取引停止など、ビジネスに深刻な影響を与えます。
マーケティング担当者に求められること
景品表示法は、広告文言の作成、キャンペーン設計、SNS投稿などマーケティング担当者の日々の業務と直結しています。
現場の担当者が法令を理解していないと「知らなかった」では済まされず、企業全体のリスクにつながります。
企画の初期段階から法務・コンプライアンス視点を取り入れることが、 ブランド信頼と売上の双方を守る鍵です。
2025年の最新動向と改正ポイント
景品表示法の改正背景
2023年に成立した改正景品表示法は、2024年から施行されており、2025年以降の運用に大きな影響を与えています。
法律の目的は変わりませんが、違反に対する監視と罰則が強化され、消費者保護のレベルが一段と高まりました。これにより、企業はより慎重な対応が求められています。
1 . 事業者の自主的な取り組みの促進
●確約手続の導入
新たに「確約手続」という制度が設けられ、万が一法律違反の疑いがあった場合でも、事業者が自発的に是正計画を提出し、行政の認定を得れば、行政処分(措置命令など)を回避できる仕組みができました。
課徴金は別途判断され、必ずしも回避できるわけではありません。
●返金の柔軟化(電子マネーによる返金等)
消費者への返金対応においては、現金に加え、電子マネーやポイント等を活用した柔軟な対応が実務上認められるようになりつつあります。
2 . 違反行為に対する抑止力の強化
●課徴金1.5倍(10年以内再違反の場合)
過去10年以内に課徴金納付命令を受けた事業者が、再び優良誤認表示または有利誤認表示を行った場合には、課徴金額が1.5倍に増額される規定が新設されました。
●直罰規定(100万円以下の罰金)
優良誤認表示や有利誤認表示に対しては、刑事罰が科される制度も導入され、100万円以下の罰金または懲役が科される可能性があり、法令違反の抑止力が格段に高まっています。
これにより、企業は表示内容の根拠確認や適正管理により一層の注意が必要です。
3 . 円滑な法執行に向けた体制整備
●国際化対応・情報提供体制の強化
国際的に事業を展開する企業にも対応できるよう、行政処分の通知方法や外国機関への情報提供体制が整備されました。
●消費者団体による開示要請規定の導入
消費者団体が事業者に対し表示の根拠資料の開示を求めることができる規定が新設され、根拠の透明性確保が強化されています。
新たに注意すべき実務ポイント
●SNSやデジタルキャンペーンの監視強化
インスタントウィンやフォロー&リポスト型キャンペーンでの表示内容や景品設定で、不当表示や過大景品にならないよう、厳しくチェックされています。
また、YouTubeやTikTokなどのインフルエンサーに対して広告であることの明示(ステルスマーケティング規制)も義務付けられています。
●デジタルギフトの取り扱い
デジタルギフトは、購入や申込といった取引条件に応じて提供される場合、景品表示法上の『景品類』に該当するため、提供価値が法定上限を超えないよう管理が必要です。
●違反者に対する監視と摘発の強化
中小企業やスタートアップも含め、違反事例の公表や措置命令の件数が増加しています。違反によるブランド毀損リスクを考え、全社的な法令順守体制の構築が不可欠です。
2025年の景品表示法は、違反行為への罰則強化だけでなく、事業者自身が自主的な対応を進められる制度の導入により、より透明で公平な市場の実現を目指しています。
マーケティング担当者は最新の法改正を理解し、広告・キャンペーン設計において細心の注意を払うことが、企業の信頼維持と成長に直結すると言えます。
景品表示法違反の具体的事例とリスク
どんな違反があるのか?
景品表示法に違反する主なケースは、消費者に誤解を与える「表示」と、法で認められていない「過大な景品」の提供です。
ここでは現場で起こりやすい具体例と、それによって企業に生じるリスクについて解説します。
主な違反の種類
1 . 優良誤認表示
実際のものよりも著しく優れていると示す表示 。
例)「1週間で5kgやせる」「国産原料100%」など、根拠のない効果や虚偽の素材訴求。
実際、健康食品やサプリメント分野の事例として、「内臓脂肪を減らす」などの根拠不足で課徴金と措置命令になったケースが近年増えています。
2 . 有利誤認表示
3 . 二重価格表示
4 . 新興の事例:ステルスマーケティング
近年の違反事例
健康食品の虚偽表示「1週間で5kgやせる」とうたう商品が行政処分
通販サイトで、割引前の「参考価格」が実際には販売実績のない価格だった
ホテル予約サイトで、税抜き価格しか表示されず、支払い時に追加料金が発生した
これらは消費者庁や公正取引委員会により企業名の公表を伴う措置命令が出されています。
違反による企業リスク
景品表示法に違反すると、以下のようなリスクが生じます。
行政処分:表示内容の是正命令、課徴金納付命令:売上額の最大3%が課徴金として課されます。さらに、過去10年以内に同様の違反で課徴金命令を受けている場合、最大1.5倍(=4.5%)に引き上げられる制度も導入されています。
ブランド信用の低下:違反企業名が公表されることでイメージダウン
取引停止:BtoBの契約打ち切り、ECモール等での販売停止
訴訟や賠償リスク:景品表示法違反が原因で損害を被ったとされる場合、消費者や取引先から不法行為に基づく訴訟や賠償請求を受ける可能性もあります。
たった1回の表示ミスや不適切なキャンペーンでも、企業活動全体に影響することを意識しましょう。
表示チェック体制の重要性
これらのリスクを回避するため、商品やキャンペーンの表示文言は必ず複数人でチェックし、根拠が明確な内容となっているかを確認することが必要です。
実際のサービス内容と表示が一致しているか
表示している価格やサービス内容の根拠が明示できるか
表示の更新タイミングや適用期間に矛盾がないか
法務・コンプライアンス部門との連携体制が整っているか
表示・キャンペーン準備段階から慎重な確認を徹底しましょう。
懸賞・プレゼントキャンペーンに関する実務ポイント
キャンペーンや懸賞は集客・売上向上につながる有効な手段ですが、景品表示法で細かなルールが定められており、違反するとブランドや売上に大きなダメージを与えます。
ここでは、実務担当者が押さえておくべき、種類・上限・注意点を整理します。
1 . 景品類の3つのタイプ
景品表示法では、キャンペーンの形式によって景品の種類・ルールが異なります。
①一般懸賞
商品やサービスの購入など、取引に対する対価を伴う条件を満たした人の中から抽選等で景品を提供する方式。
例)購入者の中から抽選で旅行券プレゼント
②共同懸賞
複数の事業者が合同で実施する懸賞。
例)商店街加盟店が合同で抽選会を実施
③総付(そうづけ)景品
購入者全員に必ず景品を付ける方式。
例)飲料に必ずキャラクターグッズが付く
2 . 景品金額の上限
景品表示法は、景品の金額に上限を設定しています。これを超えると違法となります。
●一般懸賞
○取引額5,000円未満:
最高額=取引額の20倍以内(上限10万円)かつ、総額=売上予定総額の2%以内
○取引額5,000円以上:
最高額=一律10万円以内、総額=売上予定総額の2%以内
●共同懸賞
○最高額=30万円以内、総額=売上予定総額の3%以内
●総付景品
○商品またはサービスの価額が1,000円未満:景品は200円まで
○商品またはサービスの価額が1,000円以上:景品は取引額の20%以内
※取引額は税込価格で計算します。
※価額がちょうど1,000円の場合は20%ルールが適用されます。
3 . 実務で多い注意点
●SNSやWebキャンペーンも適用対象
「全員プレゼント」とうたう場合、全員分の在庫を確保する必要があります。
当選人数や抽選基準は明示しましょう。
●デジタル景品の取り扱い
電子マネーやギフトコードも「額面金額」で上限計算されます。
複数のギフトを組み合わせる場合は合計額で判断しましょう。
●よくあるNG事例
数百円の商品で高額景品を提供(上限オーバー)
「抽選で100名様当たる」と表示しておきながら、実際にはそれに満たない人数しか当選させないなど、表示と実態が乖離しているケース
「先着順」としながら、商品が足りず途中で終了
4 . 安全な企画設計のチェックポイント
キャンペーン設計段階で、次の点を確認しましょう。
景品額が法定上限内か
応募条件や当選方法が明確か
「全員プレゼント」の場合、確実に全員に配れる数量があるか
景品の金額根拠と条件を表示に明記しているか
法務・コンプライアンス部門で事前チェックを受けているか
懸賞やプレゼントキャンペーンは集客効果も高い一方、景品表示法違反のリスクも抱えています。
「この条件・金額で適法か?」を企画初期から確認する体制づくりが、安全で効果的な実施につながります。
特にSNSやデジタル施策では、スピード感の中でも法令順守を欠かさないことが重要です。
デジタルギフトも「景品類 」! 注意すべきポイントは?
デジタルギフト活用の背景とメリット
近年、デジタルギフトは多くの企業がキャンペーンや販促施策に取り入れる人気の手法です。
紙のギフトカードや現物の景品と比較して、
発行から配布、利用までのスピードが速く
在庫管理や配送手配の手間が不要になり
紛失や誤配送リスクが減少する
という点で、 事務負担やコストの大幅な軽減が可能です。
このように効率的であることは、多くの企業が複雑化するマーケティング運営の中で望むところですが、同時に「景品」としての価値管理も求められるため、景品表示法の規制を正しく理解し対応することが必須になります。
デジタルギフトによる事務負担軽減の具体例
業務内容 | 従来の紙ギフト・現物景品 | デジタルギフトのメリット |
在庫管理 | 商品の発注、保管、納品調整が必要 | 即時発行で在庫不要 |
配布手続き | 郵送や宛名ラベルの作成が必要 | メールやSNSで一括配布 |
CS対応 | 再配送の手順や工数に時間が掛かる | メールやSNSで簡単に再配送が可能 |
コスト | 印刷費用や配送費用、再発行コストがかかる | 発行コストのみで大幅にコスト削減可能 |
デジタルギフトについて詳しくは以下の記事で解説しています。ぜひ参考にしてください。
デジタルギフトと景品表示法の関係性
景品表示法では「景品」として提供されるものは全般的に、
金額の上限規制
提供条件の明示
表示内容の正確性
が求められます。
デジタルギフトも「景品類」に該当
デジタルギフトも例外ではなく、メールやSNSで送付されるコードやポイントも「景品類」に該当し、以下の点に特に注意が必要です。
ギフトの額面価値や換算価値を明確にし、法定上限を超えない管理
ギフトを受け取るための条件や対象者を分かりやすく告知
複数種類のギフトを組み合わせる場合の合計金額の管理
これらの適切な運用を怠ると、課徴金命令や企業名公表などのリスクが生じるため、法令遵守は必須です。
安全かつ効率的な運用のためのポイント
- 配布先情報の管理を徹底し、誤送信などのミスを防止する体制を整える
- 利用期限、利用可能店舗など利用条件の明示を行う
- 複数種のデジタルギフトを混在させる場合、価値の合計額を把握・管理する
- 景品価値が法律の上限を超えないよう、管理体制を確立しダブルチェックを徹底
デジタルギフトは、景品表示法による金額上限や表示義務の遵守を前提に活用すれば、従来に比べて大幅に事務負担やコストを軽減できる有効な販促手段です。
キャンペーン設計段階から法務部門と連携し、安全で効果的な活用方法を検討することが、顧客満足度の向上と企業の持続的成長につながります。
2025年以降の対応チェックリスト
2025年現在、景品表示法の運用は年々厳格化しており、特にデジタル広告・キャンペーン・SNS施策ではチェックすべき項目が増えています。
ここでは、実務担当者が確実に押さえておくべきポイントをチェックリスト形式でまとめます。
1 . 表示全般のチェック
広告や案内文、SNS投稿など、すべての表示は以下を確認します。
□ 誇張や誤解を招く表現がないか(例:「最安値」「No.1」などは根拠明確化)
□ 「限定」「無料」「今だけ」など条件付き表現は事実と合致しているか
□ 注釈や条件は小さすぎず、消費者がすぐ見える箇所に記載されているか
□ SNS広告、インフルエンサー投稿で広告である旨の明示がされているか(※2023年施行の改正により、広告であることの明示は法的義務)
□ 情報が古くなっていないか(価格、期間、在庫など)
2 . 懸賞・キャンペーンのチェック
□ 景品の金額が景品表示法の上限内に収まっているか(一般懸賞・総付景品)
□ 応募条件や当選人数が明確に表示されているか
□ 「全員プレゼント」の場合は全員分を確保しているか
□ 抽選方法・当選発表の手順が公平・透明であるか
□ 過去施策と比較して過大な景品提供になっていないか
3 . デジタルギフト配布のチェック
□ ギフトの額面や価値を明示しているか
□ 配布先データの誤送信防止策があるか
□ 有効期限や利用条件(利用可能店舗やサービス)を明記しているか
□ 複数種類のギフトを提供する場合、合計額を把握・管理しているか
□ 管理ツール等で配布状況や利用実績を定期的に確認しているか
4 . 社内体制・教育のチェック
□ マーケティング・広告担当者に景品表示法の基本知識が浸透しているか
□ 法務部門やコンプライアンス担当者と連携する仕組みがあるか
□ 表示や景品類を事前に確認するフローが運用されているか
□ 過去の指摘・改善事例を社内で共有しているか
□ 定期的に研修や勉強会を行っているか
5 . 最新情報のフォローアップ
□ 消費者庁や公正取引委員会の最新ガイドラインを定期的に確認しているか
□ 業界団体や同業他社の対応事例を収集しているか
□ SNSやインフルエンサー関連の規制動向を追っているか
□ 必要に応じて外部の専門家に相談しているか
このチェックリストを活用すれば、日々の広告・キャンペーン業務において重大なリスクを事前に防ぐことが可能です。
景品表示法は「法令順守のための義務」だけでなく、「ブランドの信頼を守る基準」として捉え、定期的な法令の確認と都度のチェックを続けることが、企業の成長につながります。
実務担当者向けの具体的アドバイスと最新事例
景品表示法の遵守は、単に罰則を回避するためだけではなく、企業の信頼性やブランド価値を守り、マーケティング効果を最大化するための基盤です。
ここでは、現場の担当者が陥りやすい課題とその解決策、さらに最新の事例をご紹介します。
課題1:表示文言のチェックが複雑で時間がかかる
広告やキャンペーンの表現は法的な規制が厳しく、誤った表現は優良誤認や有利誤認表示の違反となるリスクがあります。文言チェックは単に言葉を確認するだけでなく、根拠のある数字や表示範囲の適正性まで検証する必要があるため、非常に手間がかかります。
対策:
●社内ガイドラインやテンプレート整備
表示可能な表現例と禁止される表現リストを作成し、担当者が手軽に参照できるようにします。例えば「No.1表示」はどんな根拠を揃えるべきか、「無料」という言葉はどの条件で使えるかを具体的に明文化します。
これにより新人や異動者も早く理解でき、統一感のある表現が可能です。
●三者による多段階チェック体制の確立
制作担当者が初回チェック、マーケティング担当が表現の目的や訴求意図に問題がないか確認し、その後に法務部門が法律的観点を最終チェックします。
こうした段階的な確認をルーチン化することで、見落としやリスクを大幅に削減できます。
課題2:法改正やガイドライン更新の情報を追いきれない
景品表示法は近年改正が相次ぎ、SNSやデジタル広告に関する規制も強化されています。
最新のガイドラインや施行例、違反事例への対応を迅速に把握しなければ、知らぬ間に違反リスクを抱えることになりかねません。
対策:
●社内の情報チェック担当を明確化
法律改正や消費者庁、公正取引委員会からの通知、業界団体の動向などを定期的にチェックし、社内に周知・共有する役割を持つ担当者を設けます。
●業界セミナーや外部研修への定期参加
専門家や行政関係者が登壇する解説セミナー、オンライン研修を積極的に活用し、社内で最新知識を吸収。得た知見はマニュアルや勉強会で展開し、全体の底上げにつなげます。
課題3:SNS・インフルエンサー施策のコンプライアンス管理が難しい
SNS施策では大量かつスピーディーな情報発信が求められますが、広告表記の漏れや過大表現が特に起こりやすい現場です。
かつ契約先のインフルエンサー個人にまで法律理解を求めるのも現実的に難しい課題です。
対策:
●契約書に広告表記義務を明記し禁止表現を規定
インフルエンサーとの契約時に、投稿内容には必ず「広告」や「PR」と明示する義務を明文化し、禁止される表現(根拠不明な効果効能など)も具体的に示します。
※2023年10月施行の景品表示法改正により、インフルエンサー投稿に「広告」であることの明示は法的義務となっています。
●投稿前の事前レビュー体制構築
投稿予定コンテンツは必ず事前に社内または外部法務にチェックを依頼できるフローを作り、問題のある表現は修正指示。スピード感を落とさず、違反リスクを抑止できます。
課題4:迅速なキャンペーン運営と法令遵守の両立
マーケティング現場ではスピーディーな企画実施が求められますが、法令遵守のための確認作業が遅れるとキャンペーン開始が遅延し、機会損失を招くこともあります。
対策:
●企画初期段階から法務を巻き込む
初回の企画アイデア段階で法務部門やコンプライアンス担当を交え、問題となりそうな表現や景品設定について早期に意見交換を行うことで、後工程での手戻りを防ぎます。
●デジタルツールを活用し承認・配布フローを可視化
ワークフロー管理システムやコラボレーションツールで承認状況をリアルタイムで共有。
誰がどの段階を担当しているのか把握できるので、進捗を管理しやすく、スピードと確認品質の両立が可能です。
最新の注目事例
SNSインスタントウィンキャンペーンの成功例
ある大手飲料メーカーは、SNSでの短期インスタントウィン企画を実施しました。
主なポイントは以下です。
●当選確率や応募条件を明確に表示
顧客が疑問に思わないよう、例えば「当選確率は約〇%」「応募は1人1回まで」などの条件を明示し、不当表示を防止。
●インフルエンサー投稿に「広告」明示を徹底
公式PRであることを全てのインフルエンサー投稿に必ず記載し、透明性を確保。
●景品金額は法定上限を厳密に守る
景品の価値が景品表示法の上限を超えないように細かく管理。
この結果、消費者の信頼獲得に成功し、キャンペーン参加率が前年より大幅に向上しました。
実務で意識すべきポイント
●「確認は最後に」ではなく、企画段階で法令遵守を組み込む
問題の芽は企画初期から摘み取り、後戻りを防ぎます。
●社内全体で景品表示法の理解を深め、担当者任せにしない
法令対応は部署の壁を超えた組織全体の課題として共有します。
●法改正や最新事例を定期的に共有する文化をつくる
社内勉強会やニュースレターなどで法律動向を継続的に伝達。
●常に消費者目線で「誤解を生まないか」をチェックする
表示やキャンペーン設計で消費者がどう感じるかを意識し、不当表示を未然に防ぎます。
景品表示法の遵守は、単なるリスク管理ではなく、ブランド信頼を築くための重要な戦略要素です。
マーケティング担当者が主体的に法令を理解し、法務・制作と連携した安全な施策運営を行うことで、企業の成長と顧客満足の両方を実現できます。
まとめ
景品表示法は、消費者を守り、公平な市場を保つための重要な法律です。
法改正や監視強化が進むなかで、マーケティングやキャンペーンの現場では
「正しい表示」「適切な景品」「根拠ある告知」がますます求められるようになっています。
景品表示法を「守るべき法律」と考えるだけでなく「顧客との信頼をより強くするための枠組み」として捉えることが、これからの成功企業の条件です。
企画段階から法務・専門家と連携し、社内全体で法律理解を深めることで、リスクを最小限にしながら効果的な施策運営を目指しましょう。
法令遵守はトラブル防止だけでなく、消費者との信頼関係を築き、長期的なブランド価値向上にもつながります。
社内での定期的な情報共有、教育体制の整備、最新事例の確認を習慣にし、キャンペーンや広告活動を安全かつ効果的に推進しましょう。