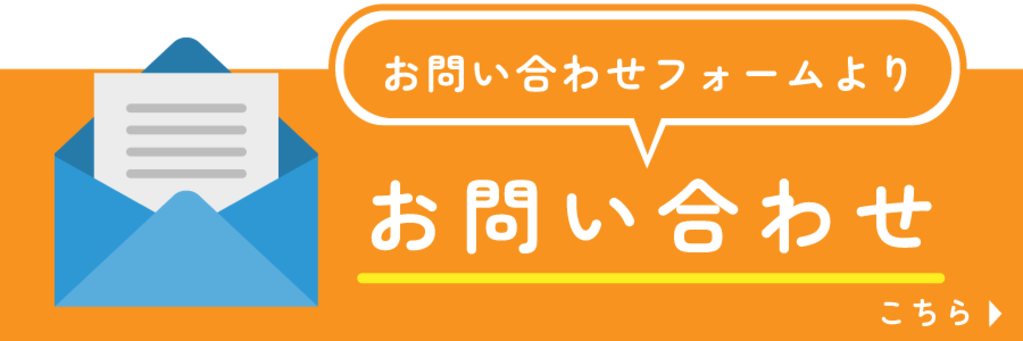株主総会のお土産を変革!デジタルギフトで株主エンゲージメント強化
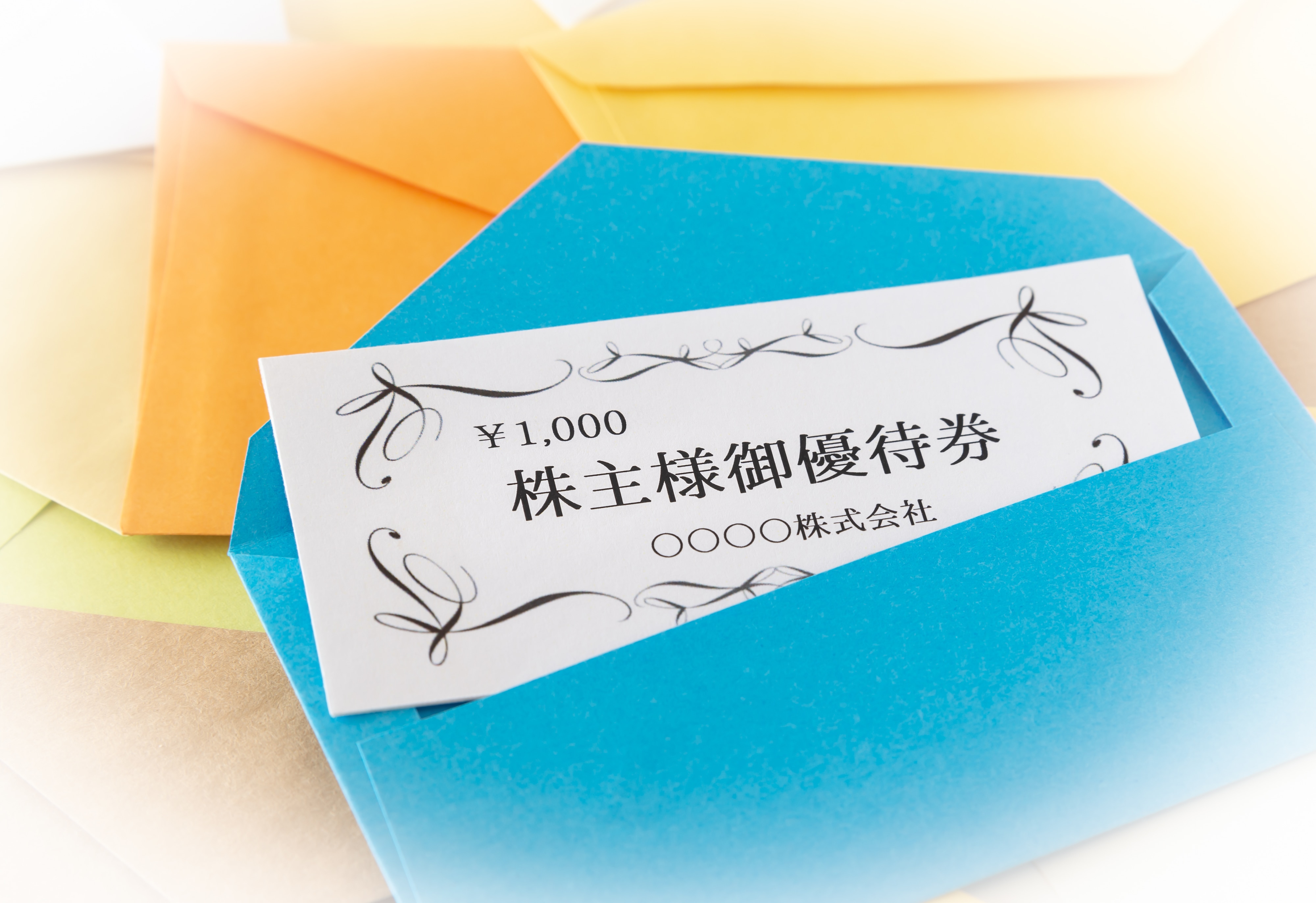
目次[非表示]
株主総会における伝統的なお土産の配布が、いまや株主エンゲージメントの新たな時代を迎えています。新型コロナウイルスの影響を受け、企業がお土産を廃止する一方で、その代替品としてデジタルギフトなど新たな優待が注目を集めています。
本記事では、この新しいトレンドがどのように株主と企業の関係に影響を及ぼしているのか、そして、株主たちが喜ぶ最新のお土産のトレンドとは何かを解説していきます。
また、人気の商品をいくつかピックアップして紹介します。これからの株主総会がどのような形に進化していくのか、一緒に考察していきましょう。
まず、株主総会とは

株主総会とは、株式会社の最高意志決定機関として位置づけられ、統治構造の中心をなす重要な集まりです。この総会には、企業の株主が集い、重要な決定事項について議論し、投票します。 具体的には、事業計画の承認、取締役の選任や解任、配当金の分配など、会社の基本的な方針を決める追認的・訴訟的な事項を取り扱います。これらは一株一票の原則に基づき投票され、投票結果によって企業の将来的な方向性が決定されます。
また、株主総会は企業と株主との直接的なコミュニケーションの場としての役割も果たしています。企業側は株主に対し、事業運営の透明性と説明責任を果たすために、会社の業績や事業計画を詳しく説明します。株主側はそれに対して意見を交え、企業経営に対する肯定や懸念を表明することができます。 そして、株主総会の終了後には、往々にして企業から株主への感謝の意を示すために、お土産が配布されます。これが、私たちがここで話題にしている「株主総会のお土産」です。最近では、このお土産を廃止する企業が増えてくる一方で、一部の企業では代替品を提供する動きも見られます。
株主優待とお土産の違いとは?
株主優待と株主総会のお土産は、両方とも株主への企業からの感謝の気持ちを示すものではありますが、その目的や提供されるタイミングは大きく異なります。
まず、株主優待は主に株を一定期間保有している株主に対して、その忠誠を示すため企業から提供される特典です。通常、これは自社の製品やサービスが提供される形となり、株主が企業の価値を直接的に理解し体験する機会となります。
一方、株主総会のお土産は、年に一度、株主総会の後に会場で配られます。これは、企業が意思決定過程に参加し、企業への貢献を示してくれた株主全員に対する感謝の意を表すものです。
代表的な株主優待品は自社商品や優待券
株主優待品は企業によってさまざまですが、多くの場合、自社の製品やサービスが提供されます。自社製品のサンプルや詰め合わせ、あるいは商品券やサービス利用券などが一般的です。これにより株主は、自社の製品やサービスを体験する機会を得ることができ、企業の価値を直接的に理解することが可能となります。
株主優待は日本独自の贈り物の風習が起源
株主優待制度は、日本特有の風習から始まりました。それは、企業が株主に対する感謝の意を示すため、独自の製品やサービスを無償または割引価格で提供するというものです。この風習は日本独特のものであり、外国の企業では一般的には見られません。株主優待は投資家へのインセンティブとなり、株式の保有を促す効果が期待されます。
お土産廃止の流れも。株主総会のお土産は必要?配るメリットは?
株主総会のお土産は一種のおもてなしであり、長い間、日本の企業による株主への感謝の意を示す手段とされてきました。しかし、最近では企業の間でお土産を廃止する動きが見られます。
コロナ以降、株主総会のお土産を廃止する企業が増加
新型コロナウイルスの感染拡大により、株主総会をオンラインで開催する企業が増え、それに伴いお土産を配る機会が大幅に減少しました。多くの企業では、株主へのお礼の意を表す方法として、お土産ではなく株主優待を提供する動きが見られています。
オンラインでの「バーチャル株主総会」や、オンラインと実際の会場のどちらも開催する「ハイブリッド形式」など、新たな開催方法については以下の記事で解説しています。
お土産廃止による株主離れも
一方で、株主総会のお土産が廃止されると、株主総会への参加意欲が低下し、企業と株主とのコミュニケーションの機会が失われることも報告されています。株主総会への参加を進めるための一種のインセンティブとなっていたお土産がなくなることで、一部の株主からはこの動きに対する不満の声も上がっています。
株主総会のお土産で期待できる効果は?
1.株主総会への参加促進
株主総会のお土産は、株主が総会に参加するインセンティブとなります。これにより、より多くの株主が総会に参加し、企業の経営に直接的に関与する機会が増えます。
2.自社製品を知ってもらえる
特に自社製品のサンプルを提供することにより、株主に直接自社製品を体験してもらうことが可能となります。これにより、株主が企業の製品やサービスを深く理解し、経営や事業に対する理解を深めることができます。また、良い評価を得た場合、口コミによって他の消費者にも製品が広まる可能性があります。
株主総会のお土産にはどんなものが配られている?
株主総会のお土産は、企業の業種や規模、そしてその会社の方針によって大きく異なります。一般的には自社製品のサンプル、食品、飲料、文房具などが含まれることが多いです。 多くの飲食関連企業では、自社の飲料や食品の詰め合わせを株主へ配布します。また、製薬会社などでは健康食品や化粧品などを提供することもあります。
一方、製造業の企業などでは、自社の製品を直接提供することは難しい場合があります。そのため、カタログギフトや商品券、または企業ロゴが入った文具や小物などを提供することもあります。
株主総会のお土産の相場は?
株主総会のお土産の相場は、企業によって大きく変わります。お土産の価格は、中小企業では数百円から数千円程度のものが一般的です。しかし、大手企業ではより高価なお土産を提供することもあります。自社の製品やサービスのクーポンや割引券、特別な体験プログラムへの招待など、数万円相当のお土産を提供することもあります。
しかし、コストパフォーマンスや環境負荷、そして企業の方針により、最近ではお土産の廃止や見直しを進める企業も多いです。その代わりに、株主へのリターンを株主優待や配当に集中させる動きが見られます。
株主に人気の最新トレンドお土産をご紹介!
最近の株主総会のお土産のトレンドは、手軽さと多様性を提供するデジタルギフトが注目を集めています。さまざまなオンラインストアで利用可能なギフト券や、各種エンターテイメントへのアクセスを提供する定額制サービスのクーポンなどが人気を博しています。
デジタルギフトは株主総会のお土産、株主優待にもおすすめ!
特に便利なのが、ストアクレジットやデジタルギフトカードです。これらは電子メールやSNS等で送信することができ、自分が好きな商品やサービスにこれらを利用することができます。
デジタルギフトは物理的な配送の手間が省けるだけでなく、遠方のためオンラインによる参加者にも即時に配布が可能で、公平性を保つことができます。会場で参加した株主にとっても荷物にならず、株主の選択肢を広げ、パーソナライズされた体験を提供する新しい形のお土産として注目されています。
また、オンラインで直接視聴可能な映画や音楽、オーディオブックなどのデジタルエンターテイメントへのアクセスコードも人気です。これらは具体的な物品の代わりに、株主に新たな体験を提供する事で特別な感覚を呼び起こします。
株主総会のお土産の進化とは
株主総会のお土産の進化は、社会環境の変化と密接に関連しています。
新型コロナウイルスの影響を受け、株主総会のオンライン開催が増えるにつれ、お土産のあり方も変わりつつあります。 物理的なお土産を配る習慣も見直され、デジタルギフトなどの新しい形の株主サービスが注目されています。
デジタルギフトは、株主が自分の好きな商品やサービスを選ぶことができ、企業側も物流コストや手間、お土産品生産による環境負荷を削減できます。また、エンターテイメント関連のデジタルギフトは新たな体験を提供し、株主とのつながりを深める機会となります。
一方で、株主優待の強化も見られ、企業は自社製品やサービスをよりポータブルな形で提供しています。これにより、株主に企業の最新の取り組みや価値を直接体験してもらうことが可能となり、株主との関係深化に寄与しています。
これらの進化は、企業が株主に感謝の意を示し、より深い関係を築くための最善の方法を追求していることを示しています。