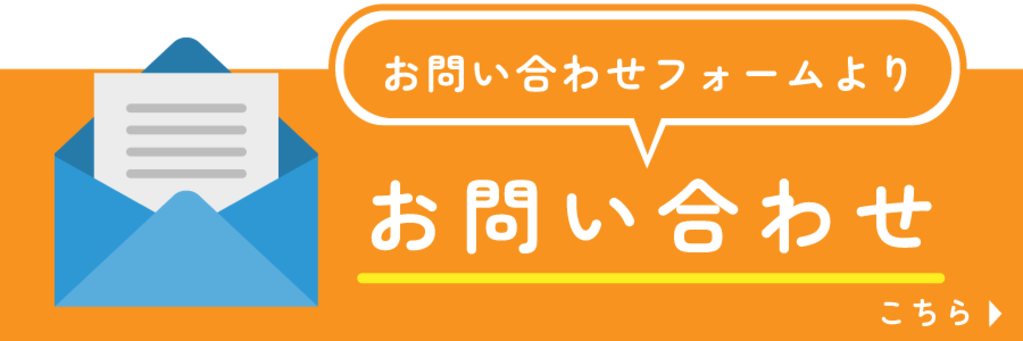【超入門】デジタルギフトコードの基本を解説!仕組み・使い方・活用例・おすすめサービス
デジタルギフトコードとは?
デジタルギフトコードの基本的な定義
デジタルギフトコードとは、商品券や金券などの価値をオンライン上のPINコード(暗証番号)やURLにしたもので、メールやSNSを通じて送付できる電子的なギフトです。
受け取り手は、そのコードを使ってオンラインサービスや店舗での支払い、商品購入、商品引換などに利用することができます。発行から受け取り、利用までがすべてデジタル上で完結し、配送や物理的なカード管理が不要なのが特徴です。
紙のギフトカードや現物ギフトとの違い
・物理的な製品が不要
紙のギフトカードや現物ギフトは、管理や配送が必要ですが、デジタルギフトコードはオンラインで即座に発行・メールやSNSなどで送付ができるため、物理的な商品と比較すると配送コストや手間がかかりません。
・即時性と手軽さ
受け取ったコードはすぐに利用可能で、贈り手も受け取り手もタイムラグがありません。
・管理の効率化
企業側はデジタル(オンライン)上で管理・送付ができるため、物理的な在庫管理や配送手配が不要です。また、送付履歴もデジタルで管理・分析ができるのも利点のひとつです。
・利用可能範囲の多様性
ECサイトでの決済、オンラインサービス利用、実店舗での支払い、サブスクなど幅広い用途に使えます。
主なデジタルギフトコードの種類と例
・Amazonギフトカードのコード
数億種類の品揃えの総合オンラインストア Amazon.co.jp にてお好きな商品をお買い求めいただけます。
また、Amazon.co.jpでのお買い物だけでなく、Amazonプライムが提供する動画・音楽・電子書籍・ゲームなど様々なデジタルコンテンツにも幅広くご利用いただけます。
※Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
・PayPayポイントコード
PayPayポイントコードとはPayPayが発行するコードタイプのギフトです。
入力もしくはURLタップで事前に設定された金額をPayPayにチャージできます。
・QUOカードPay
コンビニエンスストアをはじめ、ファッション、家電量販 店、ドラッグストア、ファストフード、カフェ、書店など幅広い業態の店舗で ご利用いただけます。 (QUOカードPayが使えるお店:https://www.quocard.com/pay/store/ )
・Google Play ギフトコード
Google Play内での決済に使用できるギフトコード。アプリ、ゲーム、電子書籍、映画、音楽など、さまざまなデジタルコンテンツを購入することができます。また、アプリ内課金にも利用できるため、ゲーム内アイテムや追加コンテンツの購入にも便利です。
これらは代表的なデジタルギフトコードで、ほかにも楽天ポイントギフトコード をはじめ、多様なサービスがあります。
これらの特徴により、デジタルギフトコードはビジネスでの販促、社員インセンティブ、顧客へのプレゼントに最適なツールとして注目されています。
オンライン完結で利便性が高く、国内外で利用者も増加中です。
デジタルギフトコードの仕組み
デジタルギフトコードがどのように発行・受け渡されるか
企業が社員や取引先、顧客へのインセンティブ、キャンペーン景品、ノベルティとして利用する際には、主にギフトサービスプラットフォームを通じて、贈りたい商品を注文し、対象者のメールアドレスや携帯番号リストをアップロードすることで、一括発行が可能です。
プラットフォームによっては一括送付のオプションがあるギフトサービスもあります。
発行されたデジタルギフトコードは、メール・SNSのダイレクトメッセージ・チャットツール・社内ポータルへの掲載など多様なチャネルを介して渡されます。
受け取り手は、送られてきたメッセージ内にある専用URLやQRコード、あるいはギフトコード番号を利用して、実際の商品受取やサービス利用へと進みます。
企業側はこれにより、従来の紙券や現物配送に比べてコスト削減や配布スピードの向上を実現できます。
デジタルギフトコードの受け取り方
受け取り手は、企業からメールやダイレクトメッセージ、社内メッセージツール(Teams、Slack など)、またはSMSなどを通じてメッセージを受け取ります。
「受け取ったメッセージ内のURLをクリック」 「記載されているPIN番号(暗証番号)を対象サービスの利用ページに入力」 「記載されているQRコードを読み込む」などをすることでデジタルギフトコードの利用を開始できます。
この仕組みにより、遠方の相手や在宅勤務者に対しても、即時にギフトを届けることが可能になります。
デジタルギフトコードの利用方法
・店舗での利用
受け取ったバーコードやQRコードをスマートフォンで提示し、実店舗のレジでスキャンすることで決済に利用できます。
ギフトコード番号を直接レジ端末に入力する方式を採用している店舗もあります。
コンビニや飲食店、ドラッグストアなど、全国的に展開する多くの実店舗で対応しているため、社員の福利厚生や販促施策で幅広く活用できます。
・オンラインショップでの利用
対象となるECサイト上で、受け取ったギフトコード番号を入力することで決済に充当できます。
例)
Amazonギフトカードのコード → アカウントにチャージして利用
PayPayポイントコード → 専用アプリやアカウントで残高化して利用
このように、デジタルギフトコードは 実店舗・EC双方で利用可能 であり、企業は配布方法の柔軟性を確保できます。
利用時の注意点や便利なポイント
・残高不足の対応
デジタルギフトコードの残高が支払い金額に足りない場合、残高分を使い切った後に不足分を現金やクレジットカードで支払う「併用払い」が可能な店舗も多いです。
事前にどの店舗・サービスで併用可能か確認すると便利です。
・デジタルギフトコードの管理
デジタルギフトコードはメールやSNSのメッセージで届くため、第三者にコードを知られないよう取り扱いに注意が必要です。
特にSNSではコメント欄ではなく、非公開のDMなどで受け渡すのが安全です。
・有効期限の確認
デジタルギフトコードには有効期限が設定されることが多いため、期限までに利用する必要があります。利用前に期限を必ず確認しましょう。
・登録や会員登録の有無
サービスによってはデジタルギフトコード利用時に会員登録やアカウントへのチャージが必要な場合があり、事前に利用方法を把握するとスムーズです。
・複数コードの合算利用
デジタルギフトコードによっては一度に1枚しか使えないケースもあるため、まとめて使いたい場合は使用条件を確認しましょう。
このように、デジタルギフトコードはメールやSNSで簡単に受け取り、店舗やオンラインショップで手軽に使えます。残高不足時の併用払いなどの便利な使い方もあり、ビジネスシーンでは贈りやすさと利便性が高いツールとして活用されています。
デジタルギフトコードのメリット・デメリット
メリット
・メール、SNSなどでの送付による配送コストの削減
デジタルギフトコードは物理的な配送が不要なため、送料や梱包、在庫管理といったコストがかかりません。企業のキャンペーンやインセンティブで大量配布する際に特に経済的です。
・すぐに贈れて即時利用可能
インターネット経由でメールやSNSを使って即座に送付できるため、急ぎのギフトやキャンペーンの景品として迅速に対応可能です。時間や場所を選ばずに贈れるスピード感がビジネスにマッチします。
・手軽さと利便性
送付も受け取りもオンラインで完結し、受け取り手はスマホやPCから簡単に利用できるため、双方の負担が軽減されます。さらに、多様な種類のギフトコードがあり、受け取り手のニーズに合わせて柔軟に選択できます。
・環境負荷の軽減
物理的なギフトカードや包装材を使わないため、環境にやさしいエコなギフト手法としてCSR活動にも適しています。
デメリット
・利用可能な店舗やサービスが限定されることがある
デジタルギフトコードは特定のブランドやサービスでしか使えない場合が多く、受け取り手がその店舗やサービスを利用しないと価値が活かせないリスクがあります。
・デジタル操作に不慣れな人には使いづらい場合がある
特に高齢者などデジタル機器の操作に慣れていない人にとっては受け取りや利用が難しいケースがあります。迷惑メールフォルダに入るリスクもあり、受け取り忘れや問い合わせの増加といった課題が生じます。
・有効期限の管理が必要
多くのデジタルギフトコードには有効期限が設定されているため、受け取り手が期限内に利用しなければ無効になってしまうことがあります。期限切れによるトラブル回避のためにリマインドや案内の工夫が求められます。
・セキュリティリスク
デジタルギフトコードの不正利用やフィッシング詐欺などのリスクがあるため、信頼できるサービス選定と送付時の注意が必要です。
・サービス選定の難しさ
市場には多様なデジタルギフトサービスが存在し、手数料や提供内容、サポート体制が異なるため、ビジネス目的に合った最適なサービスを選ぶのは簡単ではありません。
これらを踏まえ、デジタルギフトコードは「配送不要で即時に贈れる利便性の高さ」という大きなメリットがある反面、利用環境や期限管理、操作面での配慮が必要なデメリットもあります。
企業は対象ユーザーの環境や利用シーンを考慮し、適切なサービス選択と運用設計を行うことが成功のポイントです。
企業やビジネスでの個人間の活用法と事例
企業のキャンペーンや福利厚生での利用例
①販促キャンペーン
近年、多くの企業が新規顧客獲得や販売促進のためにデジタルギフトコードを活用しています。
例えば、SNSマーケティングの一環として、自社の公式アカウントをフォローし、リツイートや応募を条件に即座にデジタルギフトを当選者に贈るキャンペーンが効果的です。
多くの企業がイベント申込み特典や資料請求へのお礼としても導入し、顧客エンゲージメントを高めています。
②社員福利厚生やインセンティブ
社員のモチベーション向上や福利厚生の一環としてデジタルギフトコードも活用されています。遠方の方へも簡単に送付ができるため、業務効率化にもつながります。
③営業促進やパートナー向け謝礼
取引先やビジネスパートナーへのちょっとしたお礼や謝礼としても利用されています。
運送不要で簡単に送付できるため、ビジネスシーンでの気遣いを手軽に実現できます。
事例や具体的なシチュエーションの紹介
実際の企業導入事例におけるデジタルギフトコード活用例をいくつかご紹介します。
大手コンビニのキャンペーン
大手コンビニエンスストアのF社では、Visaのオンライン加盟店の決済に利用ができる「Visa eギフト」をキャンペーン景品に採用。オンラインVisa加盟店の決済に利用できるという汎用性、メールで当選者に送付でき、配送コストの削減や業務効率化が図れるとして採用されました。
SNSインスタントウィンキャンペーン
保険株式会社B社の公式SNSキャンペーンでは、フォロー&リプライで即時抽選とその場でギフトを配布するWeb型インスタントウィン形式を採用し、人気カフェチェーンのデジタルギフト商品券を景品として採用。
インスタントウィンキャンペーンにはデジタルギフトサービスmafinの「インスタントウィンdeギフト」が便利!
\ インスタントウィンde ギフトについて詳しくはこちらから/
オンラインアンケート謝礼
ある地方自治体ではオンラインアンケートの謝礼として、回答ボタンを押したらすぐに謝礼が贈れるデジタルギフトサービスを活用することで、事務コスト削減と顧客満足度向上につながりました。
アンケート回答後すぐにデジタルギフトをプレゼントすることができる、mafinの「アンケートdeギフト」が好評です!
\ アンケートdeギフトについて詳しくはこちらから/
社内表彰インセンティブ
とある中小企業では、社内表彰の副賞を選べるタイプのデジタルギフトに切り替えた結果、在庫管理や配布業務が大幅に効率化し、従業員のモチベーションも向上しました。
人気のギフトから受け取り手が自由に選べるデジタルギフト「選べるギフト」で満足度をさらに向上!
\ 選べるギフトについて詳しくはこちらから/
これらの活用例は、デジタルギフトコードが配送不要で即時発行かつ多様な用途に使えるため、企業の販促はもちろん個人間のギフトにも非常に適したツールであることを示しています。
ビジネスではキャンペーンや福利厚生、マーケティング効果の向上に利用され、個人では気軽に感謝や祝いの気持ちを伝える手段として広がっています。
デジタルギフトコードを取り扱うおすすめのサービス
mafin(マフィン)
マフィンは国内最大級の法人向けデジタルギフトサービスに成長しています。
全国のコンビニ、カフェ、ファストフード、スイーツ店など100ブランド以上、1,000種類以上の幅広いラインナップのギフトを提供しています。
キャンペーンや営業施策のフォローアップ体制が充実し、インスタントウィン形式のX連動キャンペーンやLINE認証連携など多彩なプロモーションが可能。
最低ロットなし、1円単位の発注も対応し、コストを抑えたい企業に好評です。
管理画面でリアルタイムの発行・利用状況確認ができ、企業イメージに合わせたロゴやメッセージのカスタマイズも可能です。(参考:https://mafin.gift/)
Kiigo for B2B
法人専用のギフトコード購入サービスで、Visa eギフトをはじめ楽天ポイントギフトコード、Amazonギフトカードのコード、QUOカードPayなど、多彩なブランドのデジタルギフトコードの一括購入・配布が可能。
デジタルギフトコードだけでなく、物理的なカードタイプのギフトカードも提供しており、シーンに合わせて使い分けできます。
配送代行オプションもあり、キャンペーンやプロモーション景品発送などの業務負担を大幅に軽減できます。安心・安全な運用体制でビジネスに最適です。(参考:https://kiigob2b.com/)
SBギフト
ソフトバンクグループのSBギフトは、コンビニやモスバーガーなど全国チェーンの商品を対象にしたバーコード利用型ギフト「ポチッとギフト」を展開。
リアル店舗での利用が中心で、幅広い層に訴求可能。企業向けにオンラインセミナーを定期開催し、活用事例や集客ノウハウを提供しています。(参考:https://www.softbankgift.co.jp/)
dgift(ディーギフト)
dgiftは100円から数万円規模まで幅広い価格帯のギフトを6,000点以上提供。
キャンペーン企画からギフト選定までトータルでサポートし、初めてデジタルギフトを導入する企業にも心強いパートナーとなります。多彩な商品群でマーケティングニーズに対応し、ノウハウや提案力が強みです。(参考:https://www.dgift.jp/)
選べるe-GIFT
選べるe-GIFTは、PayPayマネーライト、楽天EdyギフトIDなど有名電子マネーやポイントを豊富に取り揃えています。
どのプロモーション内容にもマッチしやすく、即納品対応により急ぎのイベントやキャンペーンにも対応。
発注から配布まで効率的に行えるため、企業のマーケティングや福利厚生施策に最適です。(参考:https://www.anatc-gift.com)
Giflet(ギフレット)
ジャックスカードのグループ会社が運営するサービス。
AmazonギフトカードやApple Gift Card など、利用しやすいギフトコードを中心に提供しています。
来店促進やアンケート回答など、ユーザーが達成しやすい条件設定に合わせてコードを発行でき、集客や顧客リテンションの補助に役立ちます。多くの利用者に馴染みがあるギフトラインナップが強みです。(参考:https://www.jts-web.co.jp/business/giflet.html)
ネットマイル
ネットマイルは、200種類以上の交換先を持つデジタルギフトサービスです。
ANA・JALのマイルなどの航空系ポイントをはじめ、電子マネーや有名店舗の商品券など幅広いデジタルギフトを取り扱っています。
法人向けの契約に対応しており、キャンペーン配布やインセンティブ用途に14桁のPINコード形式でギフトを発行・配信可能です。
また、キャンペーン等での活用時には提携企業のロゴを利用できる場合があり、「有名企業も採用しているギフト」という印象を与えることで参加者の信頼感・安心感を高められます(ロゴ利用には事前審査が必要)。(参考:https://biz.netmile.co.jp/service/point_digitalgift.html)
RING BELL(リンベル)
リンベルは最短当日発送と受け取り手のアフターサービスが強みの老舗カタログギフトブランドです。日用品、グルメ、体験サービスなどの多彩なラインナップをデジタルカタログ形式で提供しています。
受け取り手はスマホやPCでギフトコードを入力するだけで簡単利用が可能。
予算やターゲットに合わせてギフトを柔軟に選択できるため、女性向けのホテルスパや高額商品成約特典など、他社と差別化したキャンペーンに最適です。
また、日本全国の名産品や高級和牛、体験ギフトなど上質な商品が揃っているため、贈り先の満足度も高いのが特徴です。(参考:https://www.ringbell.co.jp)
ごちめし
ごちめし(GOCHI for ビジネス) は、飲食店のメニューをデジタルギフトとして贈れる法人向けサービスです。企業はウェブ上でギフトを一括発行し、メールやLINEで手軽に配布できます。受け取った人はスマートフォンの画面を提示するだけで利用できるため、紙券のような管理や郵送の手間がありません。「オープンごち」機能により、受け取り側が店舗の好きなメニューを自由に選べる点も魅力です。
店舗側に手数料がかからず導入しやすいため、全国16,000以上の飲食店で採用されています。キャンペーンやアンケート謝礼、福利厚生など幅広い法人施策に活用でき、利用データを通じて販促効果の可視化や顧客満足度の向上にもつながります。
(参考: https://business.gochi.online/)
デジタルギフトコードを選ぶ際のポイント
贈る相手に合ったコードの選び方
・相手の利用環境や好みに合わせる
デジタルギフトコードは受け取り手が普段よく使う店舗やオンラインサービスに対応したものを選ぶと、喜ばれやすいです。Amazonをよく利用する人にはAmazonギフトカードのコード、スマホ決済のPayPayを使う人にはPayPayポイントコードが適しています。
・年齢やライフスタイルを考慮する
若い世代にはデジタルコンテンツや音楽、ゲーム関係のギフト、年配の方には実店舗で利用しやすいコンビニやドラッグストア系のギフトが向いています。相手の趣味嗜好も踏まえ、カフェやグルメ、ファッション関係などジャンルを絞るのも効果的です。
・使いやすさも重要
受け取りやすく、使う際の手続きが簡単なものを選ぶと、利用される確率が高まります。
会員登録不要やコード入力だけで使える手軽さもポイントです。
有効期限や利用可能範囲の確認
・有効期限の確認は必須
デジタルギフトコードには有効期限が設定されているものが多く、期限切れで使えなくなるケースもあります。贈る前に期限を確認し、受け取り手に期限を伝えることが重要です。
・利用可能店舗やサービスの範囲をチェック
特定の店舗のみ対応しているものや、オンライン限定のものなど様々です。相手が実際に利用可能か、どの範囲で使えるかを事前に把握し、喜ばれるギフト選びを心掛けましょう。
・複数店舗で使える共通ギフトカードも選択肢に
利用範囲が広いことで、受け取り手の選択肢が増え、満足度が高まります。
安全に送受信するための注意事項
・信頼できるサービスを利用すること
不正利用や詐欺リスクを避けるため、実績ある正式なデジタルギフト提供サービスを利用しましょう。
・コードの取り扱いに注意する
メールやSNSで贈られたデジタルギフトコードは第三者に知られると不正使用される恐れがあります。非公開のメッセージやメールで送ること、安易にSNSで公開しないことが重要です。
・紛失や誤送信に備える管理体制
企業の場合は送付先の管理を徹底し、誤送信を防止。
万が一のトラブルに備えて対応窓口を設けておくと安心です。
・受け取り手にも注意を促す
受け取ったユーザーに対し、有効期限や利用方法、安全な保管方法を伝えるとトラブルを減らせます。
これらのポイントを押さえた選択と運用により、デジタルギフトコードは贈る相手にとって魅力的で安全なギフトとして活用できます。ビジネス用途でもプライベートでも満足度を高める重要なポイントです。
まとめ
デジタルギフトコードは、オンライン完結で即時に贈れる利便性やコスト削減効果から、企業の販促・福利厚生、個人間のギフトまで幅広く活用されています。
配送不要でスピーディーに提供でき、データ管理や効果測定も容易なため、マーケティング施策に最適です。一方で、利用可能範囲の制限や有効期限、セキュリティリスクなどの課題もあるため、導入時は対象ユーザーや利用シーンに合わせたサービス選定が重要です。
今後もデジタルギフトコードは、企業のキャンペーンや個人のちょっとした贈り物をよりスマートにし、ビジネスの可能性を広げる有力なツールとして成長し続けるでしょう。