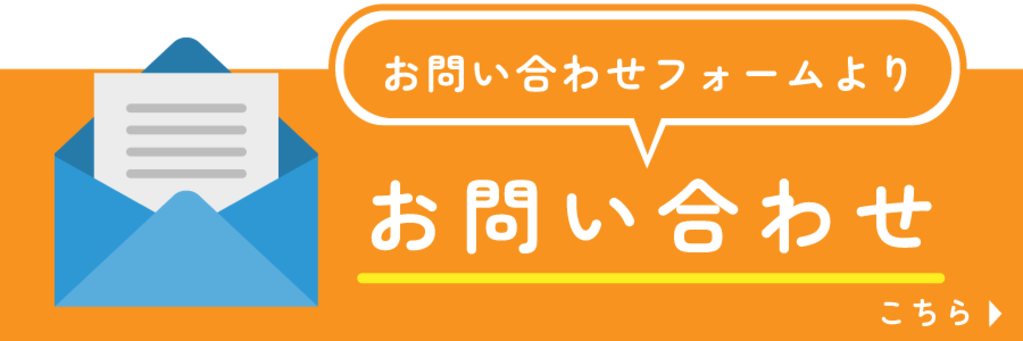法人向けデジタルギフトサービス活用のススメ|自社手配から外注で効率化・効果最大化へ

目次[非表示]
はじめに:多くの企業が法人向けデジタルギフトサービスの活用に注目
企業のマーケティング活動や社内施策において、「ギフト」や「景品」は欠かせない存在です。
販促キャンペーンのインセンティブ、アンケート謝礼、従業員への報酬や福利厚生など、あらゆる場面で贈り物を通じたコミュニケーションが行われています。
近年、そうしたギフトの手配方法が大きく変わりつつあります。
従来はAmazonギフトカードや紙の商品券を担当者が手作業で購入・発送するケースが多く見られました。
しかし、デジタル化の加速や人手不足、管理コストの増大といった背景から、法人向けの「デジタルギフトサービス」へのニーズが急速に高まっています。
特に注目されているのが、デジタルギフトを単に発行するだけでなく、「誰に・いつ・何を送ったか」を一元管理できる法人向けプラットフォームです。
ギフトの選定・発注・配布・利用状況のトラッキングまでを一括で行えるこの仕組みは、業務負荷の軽減だけでなく、ガバナンスやコンプライアンス対応の観点からも評価されています。
「ギフトは手配するもの」から「仕組みで運用するもの」へと価値が変わりつつある現在。
本記事では、企業がデジタルギフトや景品を自社で手配するのではなく、専門のデジタルギフト事業者を活用するメリットや活用事例、選び方のポイントなどを、分かりやすく解説していきます。
デジタルギフトの「自社手配」とは?
デジタルギフトの導入を検討する際、多くの企業がまず検討するのが「自社での手配」です。
これは、AmazonギフトカードやVisa eギフト、QUOカードPayなどを公式サイトや量販店で直接購入し、メールやチャットで配布するという方法です。一見すると手軽に見えますが、実際には多くの課題を含んでいます。
■ 自社手配の典型的な流れ
- ギフト券を個別に購入(オンラインまたは店舗)
- ギフトコードをコピー・貼り付け
- Excelやスプレッドシートで管理
- 社内承認・台帳管理を経て、メールやSNSで送信
- 送付後の利用確認や問い合わせ対応を手動で実施
このように、一つひとつの工程を人力で対応しなければならず、少人数での運用には大きな負担がかかります。特にキャンペーンやプロモーションで数百〜数千件規模の配布を行う場合、人的ミスや情報漏洩リスクも増大します。
■ 自社手配に潜む課題とリスク
・作業の属人化
特定の担当者にしか分からない管理方法や手順が増え、急な異動や退職時に引き継ぎが難しくなります。これにより業務が滞ったりミスが増えるリスクがあります。
・管理の煩雑さ
Excelなどで送付先や配布履歴を管理すると、誰にどのギフトを送ったかや使用状況の把握が困難になり、重複送付や未使用ギフトの放置につながる恐れがあります。
・誤送信・重複送信のリスク
手作業でのメール配布はミスが起こりやすく、誤った相手への送信や重複送信が発生すると、受け手の不満やクレーム、企業の信用低下を招く場合もあります。
・コンプライアンス面の不安
個人情報管理や社内承認フローが曖昧になると、不正や誤使用のリスクが高まります。
特に上場企業や金融機関では重大な問題となるため注意が必要です。
このような背景から、キャンペーンを成功させるどころか、担当者の負担が増えたり、信用リスクを招いたりする可能性すらあるのが「自社手配」の実情です。
社内で少人数に配る程度であれば問題にならないこともありますが、一定以上の規模や頻度になると限界が訪れるのが現実です。
次章では、こうした課題を解決する手段として注目されている「デジタルギフト事業者の活用」について、基本からわかりやすく解説していきます。
法人向けデジタルギフトサービスの活用とは?
「自社でデジタルギフトを購入し、メールで配信している」といった方法に限界を感じた企業が、次に検討するのが法人向けデジタルギフトサービスの活用です。
ここでいう「法人向けデジタルギフトサービス」とは、AmazonギフトカードやPayPayポイントなどさまざまなブランドのギフトを企業向けにまとめて提供し、配布・管理・分析などの業務を効率化できるプラットフォームやツールを提供する企業を指します。
■ 法人向けデジタルギフトサービスの主なサービス内容
法人向けに提供されるサービスには、以下のような機能があります。
・ギフトの一括購入・一元管理
法人向けデジタルギフトサービスでは、複数のブランドや種類のギフトを一括で購入し、まとめて管理できる仕組みが提供されます。
これにより、必要な数だけ柔軟に発注でき、在庫管理や発注ミスを防止。さらに、管理画面から配布状況を一元把握できるため、複数施策を同時に進める場合も効率的に運用可能です。
・メール・LINE・SMSなど多様な配布方法
受け取り手の環境や好みに合わせて、最適なチャネルでギフトを配布できます。
例えば、メールが中心の顧客にはメール配信、スマホ利用者が多い場合はLINEやSMSを利用するなど、多様な選択肢が用意されているため、受け取り率や開封率の向上に寄与します。
また、URL配布も可能なため、SNSやキャンペーンサイトとの連携もスムーズです。
・利用期限・未使用ギフトの管理
ギフトには使用期限が設定されていることが多く、未使用のまま期限切れになるリスクがあります。
一部のデジタルギフトサービスでは、未使用ギフトの再送機能や有効期限延長オプションがあり、無駄な失効を防ぐ運用も可能です。
これにより、コスト削減と顧客満足度の向上を両立できます。
・名寄せ・API連携による業務自動化
CRM(顧客管理システム)やMA(マーケティングオートメーション)ツールとAPI連携できるサービスも増えています。
これにより、顧客情報と紐づけた自動配信や、キャンペーン応募者へのサンクスギフト送付をシームレスに行うことが可能です。
手動での配布作業やデータ連携の手間を大幅に削減し、業務効率と施策の効果を高めることができます。
これらの機能により、手作業だった配布業務が大幅に効率化され、トラブルやミスのリスクも軽減されます。例えば、あるキャンペーンで500名にギフトを配布する場合でも、管理画面で一括アップロード・自動送信が可能です。
■ ギフトの選択肢も豊富で、多様なニーズに対応
また、多くのデジタルギフト事業者では、以下のように幅広いカテゴリの商品を選べるのも特長です。
- コンビニ・カフェ・飲食店(セブン-イレブン、スターバックス、すかいらーく 等)
- 汎用ポイント(Amazonギフトカード、PayPayポイント、QUOカードPay 等)
- EC・デジタルコンテンツ(Apple Gift Card 、Google Play ギフトカード 、楽天ポイント 等)
受け取り手の属性や目的に合わせて「もらって嬉しいギフト」を自由に設計できることも、法人施策における重要なポイントです。
■ 導入は驚くほどシンプル
「外部ツール導入は手間がかかるのでは…」という懸念もあるかもしれませんが、多くのサービスでは以下のようにシンプルな導入フローが整っています。
- 目的の明確化:キャンペーンの目的や期待する成果を明確にします。
- デジタルギフト事業者の選定:複数のデジタルギフト事業者へ問い合わせ、比較検討します。
- サービス内容の確認:選定した提供会社のサービス内容を詳細に確認します。
- 契約:選定したデジタルギフト事業者と契約を締結します。
- システム連携:必要に応じて、自社のシステムとデジタルギフト事業者のシステムをAPIで連携することも可能です。
- 運用開始:キャンペーンや福利厚生など目的に合わせて活用を開始します。
無料で始められるプランや、トライアル対応している事業者も多く、最小限の手間で試せるのも大きな魅力です。
次章では、こうした仕組みの導入がなぜこれほど注目されているのかを、「自社手配との比較」という視点で具体的に解説していきます。
導入に迷っている企業にとって、自社と外注の違いが明確になることで、判断材料がよりクリアになるはずです。
デジタルギフトについて、こちらの関連記事も参考にしてください。
【比較】自社手配 vs デジタルギフト事業者:メリット・デメリット一覧
ここでは「自社でデジタルギフトを手配する方法」と「専用のギフト事業者を活用する方法」を、項目ごとに比較しながら、メリット・デメリットを整理します。
■ 比較表:自社手配とギフト事業者利用の違い
比較項目 |
自社手配 |
デジタルギフト事業者の活用 |
|---|---|---|
商品の多様性 |
限られたブランドに偏りがち |
幅広いギフトブランドを一括で取り扱い可能 |
発注・管理の手間 |
手動作業が多く、属人化しやすい |
管理画面で一元管理、工数を大幅に削減 |
配布チャネル |
基本はメールまたは手渡し |
LINE・SMS・メール・QRコードなど多様な送り方に対応 |
配布ミス・トラブル対応 |
ミスが発生しやすく、再送や確認に時間がかかる |
履歴確認や未使用分の再送がシステム上で即対応可能 |
セキュリティ・統制 |
個人情報管理・台帳記録などの整備が必要 |
アクセス制御・操作履歴の記録などセキュリティ対策が標準搭載 |
コスト |
表面的には安く見えるが、人的コストや管理コストが膨らみがち |
業務効率が向上し、人的コスト・管理コストが軽減する。 |
■ 自社手配は「少量・低頻度」なら問題なし、でも…
例えば、社内の表彰で数名に配布する程度であれば、自社手配でも大きな問題は発生しません。
しかし、キャンペーンや営業インセンティブなどで多数に配布する場合や、定期的に実施する場合には手間・リスクが急増します。
また、ギフトの受け取り手から見ても、自由に選べる・スマホですぐに使えるといった利便性の高さが、満足度を大きく左右します。
ギフトそのものの価値以上に、「スムーズに届く」「使いやすい」といった体験品質がブランドイメージに直結するため、企業側もよりスマートな手法を求める傾向が強まっているのです。
次章では、こうした比較の結果を踏まえて、企業がデジタルギフト事業者を導入することで得られる具体的な「5つのメリット」について、さらに深掘りしていきます。
法人がデジタルギフトサービスを活用するメリット【4選】
ここでは、企業が自社でギフトを手配するのではなく、法人向けデジタルギフトサービスを活用することで得られる代表的なメリットを5つに整理してご紹介します。
単なる「作業の外注」にとどまらない、業務効率・顧客体験・効果測定の最適化が期待できます。
こちらの記事もぜひご覧ください。
① 業務負荷を大幅に削減できる
従来の自社手配では、ギフトの選定・発注・管理・配布・使用確認といった工程をすべて担当者が手作業で対応していましたが、法人向けデジタルギフトサービスを活用することで、これらの作業が管理画面やCSVアップロード、テンプレート化されたフローによって効率化されます。
例えば、
- 数百件のギフト配布も数クリックで完了
- 配布ミスやダブル送信のリスクをシステムで防止
- 社内承認や経費精算もシステム上で記録・管理可能
人的ミスや「確認作業のための確認作業」が減ることで、本来注力すべき業務にリソースを振り分けられます。
② 多様なギフト選択肢により受け取り手の満足度アップ
多くの法人向けデジタルギフトサービスでは、複数のブランドのギフトから受け取り手の好みに合わせて選択できる「選べるギフト」形式にも対応しています。
このように、受け取り手が自分で好きなギフトを選べる形式は満足度が高く、ブランドへの好印象にもつながります。
③ コンプライアンスや不正防止もサポート
自社手配の場合、配布リストの台帳管理や経費の裏づけなどが属人化しがちで、コンプライアンス面のリスクもあります。
一方、法人向けデジタルギフトサービスを利用することで以下のような機能が備わっています。
-
操作履歴の自動記録・証跡管理
- 配布内容や送信先の制限設定(重複配布の防止など)
- 利用期限・ギフト有効期限の自動設定
- ユーザーIDや権限設定によるアクセス管理
これにより、上場企業や官公庁、金融機関でも導入しやすいセキュアな運用が可能となります。
④ キャンペーンやCRM連携に強い(インスタントウィン、LINE配信など)
最近では、法人向けデジタルギフトサービスが提供するツールが、LINE連携・インスタントウィンキャンペーン・アンケートツールなどと統合されているケースも増えています。
例えば、
- SNSでのキャンペーン当選者にLINE経由で自動ギフト送付
- QRコードを読み取るとその場で当落がわかる「即時抽選」型キャンペーン
- 購入者アンケートの回答者に自動でサンクスギフトを送信
こうした仕組み化・自動化によって、マーケティング施策のスピードや成果を最大化できる点も、事業者活用の大きな魅力です。
次章では、実際にこうした法人向けデジタルギフトサービスがどのように活用されているのかを、具体的な利用シーンや活用事例を交えて紹介します。
よくある利用シーンと活用事例
デジタルギフトは、その利便性とスピード感から、あらゆる企業活動で活用が進んでいます。
ここでは、法人によるデジタルギフトの代表的な利用シーンと、実際の活用事例を紹介します。
自社施策のヒントとして、ぜひご参照ください。
■ 利用シーン①:販促キャンペーン・購入特典
目的:売上拡大/新規顧客の獲得/リピーター育成
デジタルギフトは、キャンペーン景品としての相性が抜群です。
特に「その場で当たる」インスタントウィン形式や、QRコード連動型の施策では、ギフトの即時配布が高い反応率を生み出します。
活用事例:食品メーカーの販促キャンペーン
- 対象商品の購入レシートを撮影して応募
- 抽選でその場でコンビニスイーツが当たる
- 当選者にはLINEでギフトURLを即時送付
→ 応募数・SNS拡散が大幅増加し、売上目標を短期間で達成。
■ 利用シーン②:アンケート・モニター謝礼
目的:貴重な意見の回収/エンゲージメント向上
アンケートやモニター施策の謝礼として、デジタルギフトは非常に好まれています。
紙の商品券や振込と比べて、コストとスピードの両面で優れており、リピーターの確保にも有効です。
活用事例:医療系メディアでの会員アンケート
-
5分以内のアンケートに回答でQUOカードPay 500円分プレゼント
-
スマホから簡単に入力 → ギフトも即時受取可能
→ 回答率が従来比1.7倍に。スピード感がモチベーションを高めた。
■ 利用シーン③:従業員表彰・インセンティブ
目的:モチベーションアップ/働きがいの向上
社内施策にも、デジタルギフトは活用されています。営業成果に対する報酬、社内イベントの景品、誕生日ギフトなど、「気軽に贈れるご褒美」として好評です。
活用事例:IT企業の営業チームインセンティブ
-
月間目標を達成したチームに、選べるデジタルギフトを配布
-
Amazonギフトカードやコーヒーチケットなどから自由に選択可能
→ 小規模でも高い満足度。手配の簡便さから継続運用も実現。
■ 利用シーン④:福利厚生・社内コミュニケーション
目的:従業員満足度の向上/離職防止
テレワークや地方勤務の広がりにより、社内コミュニケーションの活性化が課題となる中、「デジタルギフトを通じたつながり」が注目されています。
活用事例:全国拠点を持つ中堅企業の福利厚生
-
年末の感謝の気持ちをこめたメッセージと共に、選べるギフトを全社員に配信
-
社内SNSでの「ありがとう」投稿キャンペーンとも連動
→ 社員間の交流や感謝文化が生まれ、ES(従業員満足度)が向上。
こちらの関連記事も参考にしてください。
このように、顧客向け・社内向けを問わず幅広く活用できるのが、デジタルギフトの大きな魅力です。
次章では、こうした施策を実施する際に重要となる、「デジタルギフト事業者の選び方」について、チェックすべきポイントを整理してご紹介します。
法人向けデジタルギフトサービスを選ぶときのチェックポイント
デジタルギフトの導入を成功させるには、自社の目的や体制に合った法人向けデジタルギフトサービスを選ぶことが重要です。提供されるサービスや機能、サポート体制は事業者によって大きく異なります。
ここでは、企業が法人向けデジタルギフトサービスを選定する際に確認するべき主なポイントを紹介します。
① デジタルギフトの種類と価格帯の豊富さ
事業者によって取り扱っているギフトブランドや価格帯は異なります。特に以下の点は要チェックです。
- 単価100円〜数万円まで、幅広い価格帯に対応しているか
- 選べるギフト形式(複数ブランドから選択)があるか
- 法人向け限定ギフトやキャンペーン特化型商品があるか
ターゲット層やキャンペーン内容に応じて、柔軟なギフト設計ができる事業者が望ましいです。
② 配布方法の柔軟性(チャネル対応)
配布チャネルが限定されていると、ターゲット層や運用フローに合わない可能性があります。
- LINE、メール、SMS、URL配布などに対応しているか
- API連携による自動配信が可能か
- 名簿アップロードだけで配信できる簡易オペレーションがあるか
特にキャンペーンやインスタントウィン施策では、多様なチャネルに対応できるかどうかが成果に直結します。
③ 最小ロット・契約条件・導入ハードル
初めての導入であれば、少額・小規模から試せる柔軟性も重視したいポイントです。
- 初期費用・月額費用がかかるか(または無料か)
- 最小ロットの有無(例:10件〜配布可、100件〜など)
- トライアル利用やサンプル発行が可能か
費用感だけでなく、「使いやすさ」「導入のしやすさ」も含めて比較検討しましょう。
④ セキュリティとトラブル対応
法人利用では、情報管理や万一のトラブル発生時のサポート体制も重要な評価軸です。
- アクセス制限や操作履歴の記録など、ガバナンス対応ができるか
- サポート窓口があるか、返信スピードや対応範囲はどうか
施策を “ 安心して任せられる ” パートナーを選ぶことが、担当者の精神的負担を大きく軽減します。
⑤ 導入実績・信頼性
まず確認したいのは、そのサービスがどれだけの企業に利用されているかという点です。
- 上場企業や大手企業での導入事例があるか
- 官公庁・教育機関などにも対応しているか
- 過去のトラブルやセキュリティ事故がないか
社外向け施策の場合、受け取り手への安心感にもつながるため、信頼性の高い実績のある事業者を選びましょう。
【補足】導入前に整理すべき自社の要件
事業者を比較する前に、以下のような自社の要件をあらかじめ明確にしておくと、スムーズに選定できます。
- ギフトの目的(販促/インセンティブ/福利厚生 など)
- 想定配布数や頻度(例:1,000件を月1回実施 など)
- 配布対象者の属性(顧客/社員/応募者 など)
- 管理・報告業務にかけられるリソース
次章では、こうしたチェックポイントを踏まえたうえで、法人利用におすすめのデジタルギフト事業者をいくつかピックアップし、それぞれの特長を簡単に紹介します。
おすすめの法人向けデジタルギフト事業者4選
ここでは、実績があり、多くの企業から評価されている代表的な法人向けデジタルギフトサービスを3社ピックアップしてご紹介します。それぞれのサービスには強みや特色があるため、自社の目的や運用スタイルに合った事業者を選ぶことがポイントです。
① mafin(マフィン)|キャンペーン施策に強いサービスが揃う
mafin(マフィン)は、法人向けのデジタルギフト配布に特化したプラットフォームです。
特にLINE連携やインスタントウィンキャンペーンとの親和性が高く、スピーディかつ効果的にギフトを届ける仕組みが整っています。
主な特長:
- 最小ロットなし、1件から利用OK
- LINE、メール、SMS、QRコードなど多チャネル対応
- 配布状況・使用状況のリアルタイム管理機能付き
- 選べるギフトやインスタントウィンの仕組みに強い
おすすめ用途:
販促キャンペーン、LINEプロモーション、サンクスギフトなど
② Kiigo for B2B|デジタルギフトだけではなく、紙製の「ギフトカード」も取扱い
Kiigo for B2Bは、デジタルギフトとギフトカードの2つを取り揃えることでさまざまなシチュエーションでの利用に対応することができるサービスです。
特に「Visa ギフトカード」「Amazonギフトカード」「楽天ポイントギフトカード」は利用可能な範囲・利用する機会が多く、また万人に受け入れられやすい景品として人気があります。
主な特徴:
- 紙製のギフトカード対応
- オプションにて配送代行にも対応
③ デジコ(DIGICO)|PeXポイントギフトに交換することで幅広い商品と交換
デジコは、幅広いギフトラインナップと、使いやすい配布機能が魅力の法人向けサービスです。
メールアドレス不要のURL配布にも対応しており、幅広いキャンペーンに活用されています。
主な特長:
- Amazonギフトカード、PayPayポイント、QUOカードPayなどに対応
- ギフトの即時配布・使用履歴の確認が可能
- 最短即日導入、トライアル配布も相談可
- 選べるギフト形式にも対応
おすすめ用途:
アンケート謝礼、モニター募集、SNS施策など
④ giftee for Business|福利厚生やBtoE向けにも強い総合型
giftee for Businessは、福利厚生や社内表彰などの社内コミュニケーション用途に強いデジタルギフトサービスです。ギフト配布と同時にメッセージを添えることもでき、温かみのあるコミュニケーションが可能です。
主な特長:
- 選べるギフトに対応、多様なカテゴリを網羅
- 社内表彰・従業員ギフトの実績多数
- ギフト配布のオートメーション化にも対応
- 使い切り型、法人後払いなど柔軟な決済対応
おすすめ用途:
社内報奨・福利厚生、周年記念、誕生日ギフトなど
その他の法人向けデジタルギフトサービスについては以下で紹介しています。
■ 自社の目的に合った事業者選びが成功のカギ
上記のように、事業者ごとに「キャンペーンに強い」「社内利用に向いている」「URL配布が得意」など、それぞれ特色があります。
導入前には、配布対象者・件数・施策の目的・社内リソースなどを整理し、比較検討するのが理想です。
また、ほとんどのサービスで資料請求やトライアル配布が可能です。
迷ったら、まずは2~3社に資料を取り寄せて比較してみることをおすすめします。
次章では、この記事のまとめとして、改めて「法人がデジタルギフトサービスを活用する意味」や導入時のポイントについて整理します。
まとめ:業務効率と成果最大化を両立するなら“外注”が正解
デジタルギフトは、マーケティング施策や社内報酬、顧客フォローなど、企業活動のあらゆる場面で活用が広がっています。中でも「ギフトをどう手配・管理・配布するか」は、業務効率だけでなく、受け手の体験価値や成果にも直結する重要な要素です。
本記事では、以下のような観点から法人向けデジタルギフトサービスの活用について解説してきました。
-
自社手配にありがちな非効率やリスク
- 法人向けデジタルギフトサービスを利用することで得られる5つの大きなメリット
- 実際の活用シーンと、目的別に選べるおすすめ事業者の紹介
- 失敗しない事業者選びのためのチェックポイント
結論として、一定規模以上の配布や継続的な施策を実施する企業にとっては、法人向けデジタルギフトサービスの活用が「業務効率」と「成果の最大化」の両方を実現する、最も合理的な選択肢といえます。
「まだ件数が少ないから」と自社手配を続けている企業でも、今後規模が拡大したり、別部署でも活用したいという声が出てきた時に、スムーズに拡張できるような体制を整えておくことが重要です。
■ まずは小さく試してみるのがおすすめ
最近の法人向けデジタルギフトサービスは、初期費用が無料で、少数から配布できるプランを用意しているものも多くなっています。
「どんな操作感か見てみたい」「配布リストの取り込み方法を知りたい」など、気になる点があれば資料請求やデモ体験から始めてみるのが最も確実な第一歩です。
ギフトは「相手に想いを伝える手段」であると同時に、企業の信用・ブランド体験を支える重要なコミュニケーションツールです。
だからこそ、仕組みとしての信頼性と使いやすさを兼ね備えたサービスを選び、継続的に活用できる体制を整えておくことが、企業価値の向上にもつながります。