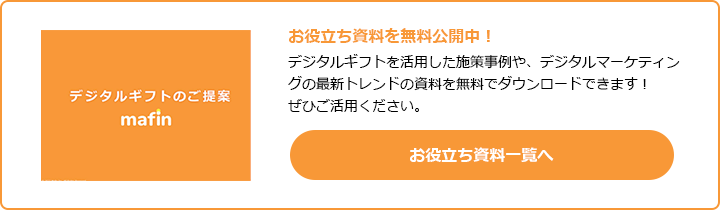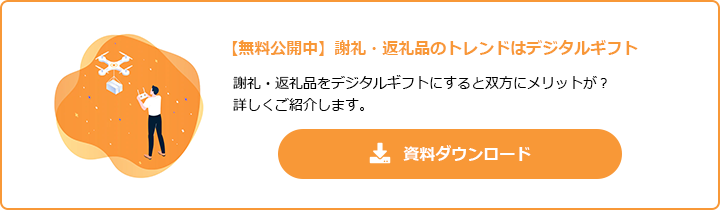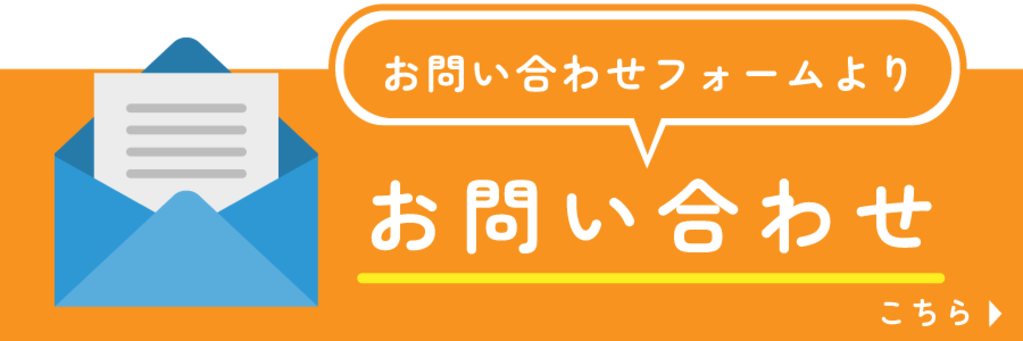アンケート調査の回答率(回収率)を高めるには?1票の重要性にも注目を!

目次[非表示]
企業は市場の動向を把握し、顧客のニーズに対応する必要があります。
ここで欠かせないのが市場調査ですが、質の高い情報を得るためには正確な設計と適切な実施、集計と分析が欠かせません。
この記事では、市場調査の中でもよく実施される定量調査(アンケート調査)の正しい設計と実施方法、情報の解析方法、そして回収率を高める秘訣を具体的に紹介します。
企業が自社でアンケートを実施するべきか、外部に委託すべきかといった疑問にも触れていきます。
ぜひ、アンケートの有効性を最大化させる参考にしてみてください。
アンケートの意味とは?
ファストフードチェーンの失敗例
あるファストフードチェーンがアンケート調査を実施したところ「健康的なメニューがほしい」という声が多かったため、その要望に従い、満を持して「サラダメニュー」を新商品で発表しました。
しかし、実際に商品が店頭に並び、販売が始まると、売上は期待に遠く及ばず、この試みは失敗に終わったのです。アンケート調査とは全く異なる結果となったのです。
アンケートの有義性と利用方法
では、アンケートをしても意味がないのかというと、そうではありません。
市場調査や顧客調査をはじめとするアンケートは、正しく行えば「宝の山」となります。
例えば、企業は新製品の開発や改良の際にアンケートを用いて市場のニーズを理解したり、顧客満足度を把握したりします。また、従業員満足度調査にもアンケートが利用され、その結果は社内環境の改善に役立てられます。
アンケート結果からは、顧客の活動時間や商品の質、サービスやウェブサイトの使い勝手など、あらゆる側面にわたる感想を得ることが可能です。これは、改善点の発見やビジネスの方向性に大きなヒントを与えてくれます。また、顧客の購買意図や製品に対する満足度など、現在のビジネス状況を評価する情報も得られます。
これらの情報は、ビジネス戦略において極めて価値があります。実際に顧客の声を聴くことで、目の前の市場状況を理解し、未来を見据えた決定を下すことが可能になります。また、アンケート結果は、新しいビジネスチャンスに気づくための重要な手がかりにもなります。
アンケート結果の誤解を避けるためのアドバイス
アンケート結果から得られる情報とその見方
前述のファストフードチェーンはなぜ失敗したのでしょうか。
それは"正しくできなかった"ということです。
この失敗からわかる重要な教訓の1つは、
消費者がアンケートに対して、「何か回答しなくては」という心理的圧迫から思ってもいないことや、望まれる答えを提供する傾向がある、ということです。
これは「調査バイアス」や「社会的望ましさのバイアス」と呼ばれる現象で、設問の順序や聞き方によって回答が誘導される、自己報告に基づく調査の一般的な落とし穴です。
そもそも、「健康的なメニューがほしい」と回答した人たちは、ヘルシーなものを食べたいときにはファストフードを選択しないでしょう。
つまり、必ずしも消費者がアンケート結果と同じ行動をするとは限らないということです。
2つめの重要な教訓は、
質問の設定や対象者の選択などにより、偏った結果が出ることがあるということです。
よくある誤解として「全ての民意が反映されている」と思い込んでしまうことがあります。回答者は、全体の一部に過ぎず、回答しなかった人々の意見は反映されません。
同じ1人、同じ一票でも、対象者の属性と構成比などによって、その重みは異なります。
各年代で同数ずつのサンプルを確保したとしても、調査結果は市場の実態の傾向とは異なる結果を持つことがあります。
「健康的なメニューがほしい」と回答した人たちは、健康志向が高めでファストフードを食べる頻度は低いと予想できます。
つまり、本来であればファストフードチェーンがもっとも優先すべき顧客は、高頻度で利用してくれる消費者だった(少数派)と言えるのです。
こうした教訓を踏まえ、アンケート結果はそのまま鵜呑みにせず、正しく評価することが重要です。
アンケートの回答率(回収率)と1票の重要性
アンケートの回答率(回収率)とは?目安は?
まずは、アンケート結果を見る際に重要視される「回答率(回収率)」について解説します。
回答率(回収率)とは、アンケートを依頼した対象者数のうち、実際に回答を完了した人数の割合のことを指します。具体的には、以下のような計算式で求められます。
回答率(回収率)=配布数/回答数×100
例えば、1000人にアンケートを送り、そのうち300人が回答を完了した場合の回答率(回収率)は30%となります。
この回答率(回収率)は調査の種類や方法、インセンティブの有無、対象者の属性などにより大きく変動しますが、一般的な目安としては以下の通りです。
- オンラインアンケート:一般的には約33%
- 郵送アンケート:一般的には約25%~30%
- B2Bアンケート:一般的には23%~32%
国政調査などの公的な調査については、回答率(回収率)は通常高くなります。例えば、令和2年の国勢調査では、回答率(回収率)は81.3%となりました。また、日経新聞とテレビ東京が実施した世論調査は、回答率(回収率)は46.6%でした。
これらの数値はあくまで一般的な目安であり、具体的な数値や詳細な情報を得るためには、各企業や研究機関が行っている類似した調査結果などを参照することをお勧めします。
回答率(回収率)とアンケート結果の信頼性は比例する?
よく「回答率(回収率)が高いほど、その調査結果はより信頼性が高くなる」とされますが、調査内容や対象者によっては一概に「回答率(回収率)が高い=信頼性が高い」とは言い切れません。
調査の種類によっては、回答率(回収率)が低くても、適切な対象者による回答が得られていれば問題ないこともあります。これは逆に言えば、いくら回答率(回収率)が高くても、回答者の属性に偏りがある場合にはその調査結果の信頼性は高いとはいえません。
では、なぜ回答率(回収率)がアンケート結果に対する重要な数値かというと、コストとアンケート調査の種類に関係します。
次の通り、「サンプリング調査」を行う場合などは、回答率(回収率)がアンケート結果の信頼性にも大きく関わってきます。
全数調査 |
対象となる人たち全員に調査を行う。データの正確性が高い反面、時間や労力などのコストが多く発生する。 |
サンプリング調査 |
対象となる人たちの中から一部を抽出して、全体の傾向を把握する調査。 |
また、どちらの調査においても、回答率(回収率)が低い場合には、回答者が回答しにくいアンケートの作りになっていないか、見直す必要があるかもしれません。
アンケート結果の1票の見方
正しくない調査や分析は、甚大な事業損失につながるミスリードを生む危険性があります。
回答率(回収率)という単純な数値だけに囚われずに結果を見ることが重要です。
調べたい人たち全員の集団の構成比と、回答者の構成比がまったく違っては、全員の意見との誤差が大きくなるため、回答者の偏りを無くす必要があります。(ウェイトバック集計)
つまり、「1人=1票」と捉えるのではなく、集まった回答を全体のバランスに合わせて換算することで、より正確な理解をすることが可能となります。
正しい解析方法やツールの推奨
アンケート結果の正確な解析には、さまざまな統計的手法やツールが必要です。頻度のカウント、平均値や中央値の算出、相関係数の計算など基本的な統計処理は必須です。
さらに、より高度な分析を行いたい場合は、クロス集計、回帰分析、因子分析などの複雑な統計手法を使用すると良いでしょう。これらの手法は、複雑な関係性を見つけ出し、洞察を得る力を持っています。
統計分析ツールとしては、Excelを始め、SPSS、R、Pythonなどがあります。これらのツールは、簡単な処理から複雑な統計分析まで、幅広い機能を提供しています。統計分析の専門知識がない場合でも、それらのツールを使うことで、容易にアンケート結果の分析が可能です。ただし、統計分析の結果の解釈には、専門的な知識と経験が一定程度必要なことを念頭に置くべきです。
アンケートは外注か内製か
それぞれの選択肢のメリット・デメリット
内製でアンケートを実施するメリット
内製でアンケートを設計・実施する最大の利点は、そのフレキシビリティと制御力です。自社でアンケートを行うことで、全てのプロセスを自分たちのタイミングとニーズに合わせて調整することが可能です。また、自社のスタッフがアンケートの作成と実施、そして解析に関与することで、結果の理解と応用が容易になります。
内製でアンケートを実施するデメリット
一方で、自社でアンケートを行うことは、リソースと時間を大幅に必要とします。有効なアンケートを設計・分析するための専門知識が必要となるため、そのようなスキルを持つスタッフがいない場合は、結果の信頼性と有用性に疑問が生じる可能性があります。
外部委託によるアンケート実施のメリット
外部にアンケートを委託する最大の利点は、その専門性と効率性です。専門的な調査会社では、経験豊富なプロフェッショナルが最新の手法を用いてアンケートを設計、実施、分析し、最適な結果を出すことを確実にします。また、自社のスタッフがアンケートのプロセスに多大な時間を割くことなく、自社の重要な業務に専念することが可能になります。
外部委託によるアンケート実施のデメリット
信頼性のある業者を見つけることに時間とリソースが必要となります。また、費用も一考するべき要素です。専門的なアンケート調査は高品質な結果を出しますが、それには相応の費用が発生します。また、データの安全性についても考慮する必要があるでしょう。
ビジネスの目的とリソースに応じた適切な選択方法の提案
自社での実施と外部への委託、どちらの選択肢が最善かは、ビジネスの具体的な目的と利用可能なリソースによるところが大きいです。
短期的、または一度限りの調査で、自社にアンケート設計やデータ分析の専門知識を持つスタッフが少ない場合、または時間や人材が限られている場合は、外部への委託が適しているかもしれません。
一方、アンケート調査がビジネスの常駐的な一部である場合、または自社のスタッフがアンケート設計とデータ分析のスキルを持っている場合、自社でのアンケートの実施を検討する価値があるでしょう。長期的に見てリソースの節約につながることがあります。
規模、予算、タイミング、スキル、全体戦略等、さまざまな要素を考慮して最適な選択を行うことが重要です。
アンケート回答率(回収率)を上げる秘訣
回答率(回収率)を向上させるための具体的な手段やヒント
アンケートの回答率(回収率)を高めるためには、アンケートの設計から実施までの各段階で慎重な配慮と戦略が必要です。以下に、アンケート回答率(回収率)を向上させるための秘訣をいくつか紹介します。
目的の明確化
まず第一に「アンケートを通じて何を知りたいのか」といった、目的を明確に設定することが重要です。そしてその目的を、アンケートを受ける人々にも理解できるように明確に伝えましょう。その結果がどのように活用され、何に貢献するのかを示すことで、人々は自分の意見が大切にされると感じ、回答する意欲を引き出すことができます。
日時の選択
アンケートを送るタイミングは、回答率(回収率)に大きく影響します。調査によると、アンケートの送信に最も適した時間は午後であり、週の真ん中の日が最も効果的だとされています。また、休日に送信すると回答率(回収率)が下がる傾向があります。ただし、ターゲット層の生活習慣などを把握して、最適な日時を考えましょう。
確認の通知
アンケートが送信された時、または締切日が近づいているときにリマインダーを送ることも効果的です。ただし、リマインダーが多すぎると逆効果になる場合もあるので、適切なバランスが重要です。
報酬
調査に対する報酬やインセンティブも、アンケート回答率(回収率)を向上させる一つの手段です。ただし、報酬の提供は必ずしも回答の質や有益性を高めるとは限らないため、注意が必要です。引き続き、次項でアンケート設計と質問の作成方法について詳しく解説します。
アンケートへの謝礼にはデジタルギフトがおすすめです。詳しくは以下の記事でご紹介しています。
効果的なアンケート設計や質問の作成方法
アンケート設計において、質問の内容はアンケートの回答率(回収率)と質を大きく左右します。以下に、質の高いアンケートを作成するための有用な手法やヒントをいくつか紹介します。
シンプルで明確な質問
質問はシンプルかつ明確に作るべきです。理解されにくい質問や語彙は回答者を混乱させ、アンケートへの回答意欲を失わせます。質問は一般的で、なるべく業界用語や専門用語を避け、多くの人が理解しやすい言葉を選びましょう。
バランスのとれた質問形式
「はい・いいえ」形式の閉じた質問と、自由回答式の開放的な質問をバランス良く入れましょう。閉じた質問は簡潔な回答を促し、開放的な質問は詳細なフィードバックやアイデアを引き出すのに役立ちます。
明確な指導
アンケートの開始部分で、アンケートの目的、時間の見積もり、回答の匿名性や利用方法について明確に伝えることが重要です。これにより、回答者に安心感と信頼性を提供し、回答への意欲を引き出します。
論理的な流れ
質問は一般的なものから始め、その後具体的なものに移るように配置しましょう。論理的な流れにすることで、回答者はアンケートを進めやすくなり、適切な情報を提供しやすくなります。
バイアスを避ける
質問文や選択肢の設定は、回答者の意見を偏らせる可能性のある表現は避けるよう注意が必要です。中立的で公平な言葉を使い、全ての選択肢が平等に扱われていることを保証しましょう。
これらのポイントを意識してアンケートの設計と実施を行うことで、回答率(回収率)と品質の向上につながるでしょう。ただし、最も重要なのはアンケートの目的に沿ったアプローチを採用することです。ターゲットの視点から、最適な質問とアンケート設計を慎重に考えてみましょう。
具体的なアンケートの作り方やコツを例文付きで解説しています。
こちらの記事も参考にしてください。
まとめ
アンケートは、顧客の意見を収集し、ビジネス戦略を洗練させるための強力なツールです。 アンケートの回答率(回収率)を上げる鍵は、明確な目的設定、適切な日時選択、アンケートへのリマインダー、そして場合によっては報酬の提供を通じての参加者の動機づけです。これらの要素を適切に配合することで、より多くの顧客からのフィードバックを引き出すことが可能となります。
さらに、効果的なアンケートの設計と質問作成には、シンプルで明確な質問、バランスの良い質問形式、明確な指導、論理的な流れ、そしてバイアスの排除が求められます。
これらの要素が組み合わさった質問は、回答者の深層心理を引き出し、本質的な情報を獲得するのに役立ちます。
アンケート設計について理解することで、適切な情報収集を達成し、ビジネスの方向性をより明確にし、進化させることが可能です。効果的なアンケート作成こそが、ビジネスがニーズを的確に把握し、戦略を構築する鍵と言えるのです。