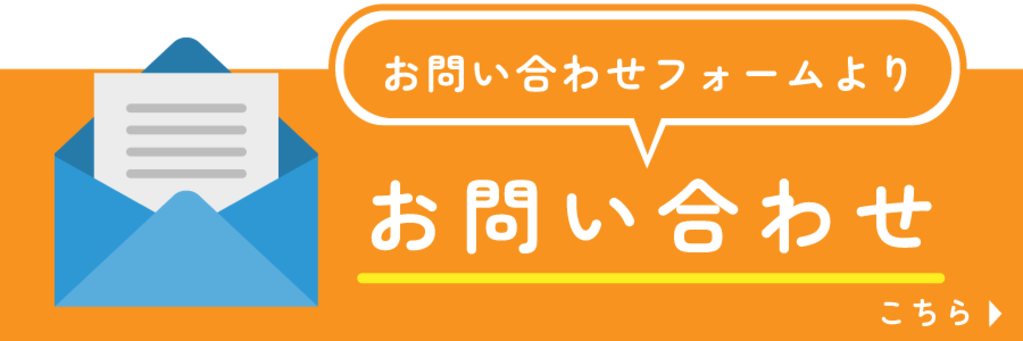電子ギフトとは?メリットや活用シーン、仕組みを解説!人気の理由も解明!

目次[非表示]
- 1.電子ギフトとは?
- 2.なぜ電子ギフトが選ばれるのか?
- 3.電子ギフトのメリット・デメリット
- 4.電子ギフトの活用シーン
- 5.電子ギフトの選び方
- 6.電子ギフトの仕組み(法人)
- 7.まとめ
電子ギフトとは?
電子ギフトの定義と特徴
電子ギフトは、オンライン上でギフトカードや商品を贈ることができるサービスです。
電子ギフトは、デジタルギフト、ソーシャルギフト、eギフト、オンラインギフトなどと呼ばれることもあります。
ギフトカード、電子マネー、ポイント、体験型ギフトなど、さまざまな商品を、メールやSNSのダイレクトメッセージなどを通じて送信することができます。
受取人は、送られてきたURLを通じて商品を交換したり、ポイントや電子マネーを受け取ることができます。物理的な配送が不要で、個人情報の取得も必要ないため、手軽に贈ることができるのが特徴です。
電子ギフトの種類
電子ギフトは、大きく分けて以下の種類があります。
・ギフトカードタイプ:ブランドや店舗ごとに利用できるデジタルギフトカードです。
人気の店舗やサービス、ショッピングなどで使用できるものが多く、受け取る側も使い道を選びやすいのが特徴です。
・ポイントタイプ:ポイントを提供するタイプで、企業独自のポイントシステムや提携サービス内で使えるポイントとして贈ることができます。
ロイヤリティプログラムや顧客関係強化にも役立ちます。
・電子マネータイプ:直接電子マネーを受け取れるギフトです。
電子マネーを活用した支払いができるため、実用性が高く、日常の買い物などに利用することができます。たとえば、楽天EdyやPayPay、WAONなどが含まれます。
・商品券タイプ:具体的な商品やサービスと交換できるギフトです。
たとえば、コンビニやカフェの商品と交換可能なクーポンがあり、受け取り手が全国どこででも気軽に使えるものが多く、大変人気があります。
・体験ギフトタイプ:食事やアクティビティ、宿泊などの「体験」を提供するギフトです。
受け取り手が自分の興味に合わせた体験を選べるため、特別感があり、企業のプレゼントキャンペーンやプロモーションにも活用されています。
なぜ電子ギフトが選ばれるのか?
電子ギフトが選ばれる理由とは?
電子ギフトのメリット
電子ギフトは、手軽さと利便性が最大の魅力です。
購入から受け渡しまで受け渡しまでオンラインで完結できるため、物理的な配送や梱包の手間が不要です。
また、受け取った人は好きなタイミングで利用でき、紛失のリスクも少ないという利便性があります。さらに、物理的なギフトに比べて送料や包装費用がかからず、コストパフォーマンスが高い点も魅力です。
贈り手・受け取り手双方にとってのメリット
贈り手にとっては、住所を知らなくてもSNSアカウントやメールアドレスを知っていれば贈ることができるため、個人情報の管理や配送手配などの負担が軽減されます。
受け取り手にとっても、個人情報を知らせなくても受け取れる点や、パーソナライズされた体験を得られる点がメリットです。
企業側のメリット
企業にとって電子ギフトは、マーケティング戦略や従業員エンゲージメントの強化に役立ちます。
例えば、新商品の購入者に次回利用できる電子ギフトを提供することで、リピーターの増加を図るケースがあります。また、特定のイベントで参加者全員に電子ギフトを配布することで、イベントへの参加意欲を高めることができます。
そのほか、従業員への福利厚生として電子ギフトを活用することで、従業員のモチベーションや社内満足度の向上に繋がります。業務に意欲的に取り組む傾向が強くなるため、結果として業務の効率化にも繋がりやすくなります。
従来のギフトとの比較
従来の物理的なギフトと比較すると、電子ギフトは配送コストや時間的制約がなく、配送にかかる環境負荷も低減されます。
また、多様な商品やサービスから選べるため、受け取り手の好みに合わせた贈り物が可能です。これにより、贈り物としてより柔軟で効率的な選択肢となっています。
電子ギフトのメリット・デメリット
電子ギフトは、現代のライフスタイルに合わせた便利な贈り物の形態として注目されていますが、メリットとデメリットの両方があります。
メリット
1. 手軽でスピーディーな贈答
電子ギフトはオンラインで購入し、即座にメールやSNS等で送信できるため、急な贈り物にも対応可能です。時間や場所を問わず、迅速に感謝やお祝いのメッセージを伝えるとともに即時にギフトを贈ることができます。
2. パーソナライズ
受取人の好みに合わせたギフトカードやポイントを選ぶことで、よりパーソナライズされた贈り物が可能です。例えば、特定のブランドやサービスに特化したギフトを選ぶことで、受取人の趣味やニーズに合ったプレゼントを提供できます。
3. コスト削減
物理的なギフトと異なり、送料や包装費用がかからないため、コストを抑えることができます。また、大量購入時には割引が適用される場合もあり、キャンペーンやプロモーションを行う企業にとっては、プレゼント商材として大変経済的です。
4. 環境負荷の低減
紙やプラスチックなどの包装材を使用しないため、環境への負担を軽減できます。
配送による二酸化炭素排出も削減できるため、エコフレンドリーな選択肢として注目されています。企業のCSR(社会的責任)活動としても効果的です。
5. 広範囲な選択肢
キャッシュレスポイントや電子マネーなどのデジタルコンテンツから実店舗で利用可能なギフトカードまで、多様な選択肢があり、贈る相手の好みに合わせて最適なギフトを選ぶことができます。
デメリット
1. 物理的な贈り物ではない
電子ギフトはデジタル形式であるため、物理的な存在感や感触がありません。
そのため「形として残るもの」を重視する人には、実物の贈り物に比べて感動が薄い場合があるため、不向きかもしれません。
2. 利用できる店舗が限られる場合がある
特定のブランドやプラットフォーム専用の電子ギフトは、その範囲内でしか利用できないことがあります。受取人がその店舗を利用しない場合、価値が限定されてしまう可能性があります。
3. セキュリティリスク
電子メールやメッセージで送信されるため、不正アクセスやフィッシング詐欺などのセキュリティリスクがあります。
信頼できるプラットフォームを利用し、安全性を確保することが重要です。
電子ギフトは、その利便性と柔軟性から多くの場面で活用されていますが、一方で物理的な贈り物にはない特有の課題もあります。これらのメリットとデメリットを理解し、状況に応じて最適な方法で電子ギフトを活用することが求められます。
電子ギフトの活用シーン
電子ギフトは、企業と個人の両方で幅広く活用されています。
それぞれの具体的な活用シーンを見ていきましょう。
企業における活用
1. キャンペーン・プロモーション
販促キャンペーン
商品購入者や来店客に対して、次回購入時に使えるクーポンや割引券を電子ギフトとして提供することで、リピート率の向上を図ることができます。
また、新規顧客獲得のための紹介キャンペーンにおいて、紹介者と被紹介者双方に電子ギフトを贈ることで、口コミによる顧客拡大を促進できます。
関連記事はこちら
SNSキャンペーン
自社商品やサービスに関する投稿を募集するSNSキャンペーンにおいて、参加者全員や抽選で選ばれたユーザーに電子ギフトを贈ることで、ユーザー生成コンテンツ(UGC)の増加や、ブランド認知度の向上を図ることができます。
関連記事はこちら
インスタントウィンなどのツールによるサポート
キャンペーンやプロモーションの成功をさらに高めるために、インスタントウィンなどのリアルタイム抽選ツールも有効です。
SNS上でリアルタイムに抽選結果がわかるインスタントウィンは、電子ギフトとの親和性が高く、個人情報の入力を省略できるため、参加のハードルが低くなり、エンゲージメントが向上します。
また、当選者に即座に電子ギフトが提供されることで、参加者満足度も高まります。
関連記事はこちら
2. 社内コミュニケーション強化
従業員表彰・報奨
優秀な成果を上げた従業員や、長期勤続者に対して電子ギフトを贈ることで、迅速かつ効果的な表彰が可能です。金銭的な報酬とは異なり、電子ギフトは「特別なご褒美」として受け取られやすく、モチベーション向上に直結します。
例えば、月間MVP賞の副賞として有名コーヒーチェーンの電子ギフトを贈るなど、受賞者の好みに合わせた選択ができます。
関連記事はこちら
福利厚生
従来の福利厚生制度を補完する形で、電子ギフトを活用することができます。
例えば、健康経営を推し進めるために、健康診断受診者や禁煙達成者へのインセンティブとして電子ギフトを提供することで、従業員の健康増進を促進できます。
また、従業員の誕生日や入社記念日に電子ギフトを送ることで、個々の従業員への配慮を示すことができます。人事システムと連携させることで、自動的に該当者へギフトを送付することも可能です。
これにより、従業員のエンゲージメント向上や離職率の低下につながる可能性があります。
他にもコロナ禍以降のリモートワーク環境下での社員間コミュニケーション活性化策として、オンライン飲み会用の電子ギフトを配布するなど、新しい働き方に対応した福利厚生の形を提案できます。
関連記事はこちら
3. 顧客との関係構築・強化
顧客アンケートへの参加インセンティブ
顧客満足度調査や商品開発のためのアンケートに回答してくれた方々へ、感謝の気持ちを込めて電子ギフトを贈ることで、回答率の向上や質の高い回答の獲得につながります。
また、顧客に「自分の意見が反映される」という満足感を与えられることで、次回以降のアンケート協力も得やすくなります。
関連記事はこちら
資料請求・メルマガ開封の謝礼
資料請求やメールマガジンの開封といった、顧客とのタッチポイントにおいて電子ギフトを活用することで、より深い顧客エンゲージメントを築くことができます。特に、BtoBビジネスや高価な商品・サービスの分野では、電子ギフトの提供が効果的なフォローアップ・ナーチャリングとして機能し、その後の商談や連絡に発展するきっかけを作ります。
関連記事はこちら
ロイヤリティプログラム
顧客の継続的な利用への感謝を示し、ブランドへの忠誠心を高める重要な戦略がロイヤリティプログラムです。
例えば、購入金額や利用頻度に応じて電子ポイントを付与することで、顧客は次回の購入時にポイントを使用でき、リピート購入を促進できます。
また、一定以上の利用回数や累計購入額に達した際に、特別な電子ギフトを贈呈します。これにより、顧客の長期的な関与を促進できます。
そのほか、利用頻度や総額に応じて会員ランクを設定し、ランクに応じた特別な電子ギフトを提供するマイルストーン形式も効果的です。
カスタマーサポートでの対応後フォロー
問い合わせ・クレームなどの特別な対応が必要だった顧客やサービス障害・製品の不具合等、発生させないことがベストではありますが、万が一のときの適切な対応は顧客との信頼関係を強化する機会となります。
障害発生後、速やかに電子ギフトを贈ることで、迅速な対応と誠意を示すことができます。
また、 顧客が複数の補償オプションから選べるようにすることで、顧客満足度を高めることができます。例えば、電子ギフトカード、追加サービス、または次回以降の割引などから選択できるようにします。
4. BtoBでの贈答品
商談時の手土産・商談後のお礼
オンライン商談が増加する中、従来の対面での手土産に代わるものとして電子ギフトが活用されています。商談相手の好みに合わせたギフトを選択し、商談終了後にすぐ贈ることで、迅速かつ手軽に感謝を伝えることができます。
特に初めての取引先や長期的なパートナーシップを目指す場合に有効で、相手に好印象を与え、ビジネス関係をスムーズに進めるきっかけとなります。
関連記事はこちら
季節の挨拶
お中元やお歳暮などの季節の挨拶を、電子ギフトで代替することが増えています。
特に、取引先が多い企業にとっては、日頃の感謝を示すとともに、良好なビジネス関係を維持することに繋がるのはもちろんのこと、配送手配や在庫管理の手間を大幅に削減できるメリットがあります。
関連記事はこちら
イベント参加特典
ビジネスセミナーやウェビナー参加者への特典として、電子ギフトの提供が効果的です。
この方法には以下のような利点があります。
-
参加促進:事前に参加者に電子ギフトプレゼントキャンペーンを告知することで、参加意欲を高められます。
-
エンゲージメント向上:参加者がイベント後に電子ギフトを受け取ることで、企業との関係性を深めるきっかけとなります。
-
フィードバック促進:イベント後のアンケート回答者に対して電子ギフトを贈ることで、フィードバック率を向上させることができます。
関連記事はこちら
5. その他
株主総会のお土産、議決権行使の謝礼
株主総会の来場者へのお土産や、議決権行使への謝礼として電子ギフトを活用する企業が増えています。特に、オンライン株主総会の普及に伴い、株主総会会場でのお土産の配布ができない場合に、電子ギフトは効果的な代替手段となっています。
また、議決権行使を促進するためのインセンティブとして電子ギフトを活用することで、株主の経営への参加意識が高まり、コーポレートガバナンスの強化にも寄与します。
関連記事はこちら
\お役立ち資料を無料ダウンロード/
個人における活用
1. 誕生日プレゼント
-
遠距離の友人や家族へ:物理的な距離を問わず、すぐに贈ることが可能です。
- 幅広い選択肢:受け取り手の好みに合った商品を選んで贈ることができます。
2. お祝い
-
結婚祝い:新郎新婦が必要なものを自由に選べる電子ギフトカード。
- 卒業祝い:進学や就職に向けて使える電子マネーやポイント。
- 新生活応援:引っ越しや新社会人向け、家電や日用品購入に使えるギフト。
3. 感謝の気持ちの表現
-
お世話になった人へ:急なタイミングでも感謝の気持ちを伝えることができます。
-
小額での気持ち表現:気軽に感謝を伝えられる少額の電子ギフトも多数あります。
電子ギフトは、その即時性と柔軟性から、企業の戦略的な活用から個人の日常的な利用まで、幅広い場面で効果的に活用されています。
状況や目的に応じて適切な電子ギフトを選択することで、より効果的なコミュニケーションや関係構築が可能となります。
電子ギフトの選び方
電子ギフトを選ぶ際のポイント
電子ギフトを選ぶ際には、以下のポイントを考慮することが重要です。
-
目的と用途:電子ギフトを贈る目的を明確にし、それにあった種類を選びます。例えば、誕生日プレゼントや感謝の気持ちを伝えるためのギフトなど、目的に応じた選択が求められます。
-
予算:予算に応じて選べる電子ギフトの種類は異なります。手頃な価格から多くの選択肢があるため、予算に合わせて最適なギフトを選びましょう。
- ターゲット層:贈る相手の年齢、性別、趣味、ライフスタイルに合わせたギフトを選ぶことが大切です。
目的・予算・目標層に合わせた選択
-
若年層向け:Google Play ギフトカード や Apple Gift Cardなど、デジタルコンテンツに利用できるギフトが人気です。
-
幅広い年齢層向け:Amazonギフトカードなど、多様な商品に利用できるものが適しています。
- 特定の趣味・興味に対応:音楽好きには音楽配信サービスのサブスクリプション、読書好きには図書カードNEXTなどが喜ばれます。
信頼性で選ぶ
電子ギフトを提供する企業の選択も重要な要素です。
信頼できる企業の商品にすることで、トラブルを回避し、安心して利用できます。
特に、大手企業や実績のあるサービスを選ぶと良いでしょう。
代表的な電子ギフトサービス例
- Amazonギフトカード:多様な商品に利用可能で、多くの人に喜ばれる定番の電子ギフト。
- Google Play ギフトカード:アプリやデジタルコンテンツ購入に最適。
- PayPayポイント:1ポイント=1円としてPayPayでの支払いに利用できるポイントで、普段からPayPayを利用する人には特に喜ばれます。
これらのポイントを考慮しながら、相手やシーンに最適な電子ギフトを選ぶことで、より満足度の高い効果的な贈り物が可能になります。
また、上記の電子ギフトをキャンペーン施策で効果的に活用したい企業担当者の方には、株式会社マフィンの提供するデジタルギフトサービスの利用がおすすめです。
法人向け電子ギフト(デジタルギフト)サービス。
AmazonギフトカードやGoogle Playギフトカード、PayPayポイントをはじめとした、業界最多となる100以上のブランド・1,000種類以上の商品を取り扱っています。
電子ギフトの仕組み(法人)
電子ギフトは、デジタル技術を活用して贈り物をオンラインで送受信するシステムです。
その仕組みは非常にシンプルで効率的であるため、近年ではキャンペーン商材の中では大人気となっています。
以下に、電子ギフトを販促・集客キャンペーンや福利厚生としての社内インセンティブとして導入する際の基本的な仕組みを説明します。
1. 電子ギフト(デジタルギフト)事業者への問い合わせ~申し込み・契約
-
電子ギフト事業者へ問い合わせや資料請求をし、キャンペーンや福利厚生等、自社での利用目的に適した電子ギフトサービスを比較検討します。
- 選択した電子ギフト事業者と契約をします。
2. ギフト商品の選択・発注~案件内容・クリエイティブ等の審査
-
キャンペーンでの利用や、従業員への福利厚生の一環として購入したいギフトの種類、金額、数量、手数料等を確認し、発注。発注方法は、電子ギフト事業者のサービスサイトや、担当者との商談時に行うなど、事業者によって異なります。
- 電子ギフト事業者が、ギフト商品の発行元企業へ審査を依頼します。
3. ギフト商品の受け取り~電子ギフトを贈る
-
審査の結果、発行元企業による承認が得られたら、電子ギフト事業者からギフト商品のURLが発行されます。
- 電子ギフト事業者から発行されたギフト商品のURLを受取人に送信します。
- 送信方法は主に以下の3つがあります。
- メール:受取人のメールアドレスに直接送信。個人向けや企業内での利用に適しています。
-
SNS:LINEやX(旧Twitter)などのダイレクトメッセージ機能を使用。キャンペーンや広告と連動させやすく、若年層へのアプローチに効果的です。
- QRコード:ギフトコードをQRコード化し、印刷物やデジタルサイネージに掲載。イベントや店頭でのプロモーションに適しています。
4. ギフトの受け取りと利用
-
受け取り人は、メールやSNSで受け取ったURLにアクセスするか、QRコードをスキャンします。
- ギフト受け取りページが表示され、ギフトの内容や利用方法が確認できます。
- 受け取り画面のQR コードやバーコード等を使って店頭やネットショップで商品と交換します。アプリのダウンロードや会員登録は必要ありません。電子マネーやポイントの場合は、指定されたアカウントに直接チャージします。
こうした仕組みにより、電子ギフトは物理的な配送を必要とせず、即時に送受信が可能となります。
受取人は場所や時間を問わずギフトを受け取り、すぐに利用を開始できるため、利便性が高く、顧客満足度の向上にも繋がります。
企業にとっては在庫管理や配送コストの削減、キャンペーンとの連動のしやすさなど、多くのメリットがあります。
まとめ
電子ギフトは、デジタル時代の新しい贈り物の形として急速に普及しています。
本記事では、電子ギフトの定義や特徴、メリット・デメリット、活用シーンなどについて詳しく解説しました。
電子ギフトは、テクノロジーの進化と消費者ニーズの変化に応じて、今後さらに多様化し、私たちの生活に深く浸透していくことが期待されます。
この新しいギフトの形態は、人々のつながりを強め、個人でもビジネスでも、より便利で効果的なコミュニケーションの手段として発展していくでしょう。